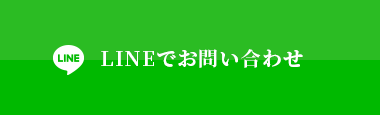食いしばり対策に注目されるボトックス治療とは?特徴と考え方を紹介

食いしばり・歯ぎしりの原因と影響
日常生活の中で、無意識に歯を食いしばる癖がある方は少なくありません。このような習慣は、睡眠中やストレスを感じた際に特に顕著に現れます。食いしばりや歯ぎしりは、歯や顎に過度な負担をかけ、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。ここでは、その原因と影響について詳しく見ていきましょう。
無意識の「癖」が引き起こす奥歯への負担
食いしばりや歯ぎしりは、無意識のうちに行われることが多く、特に睡眠中に顕著です。このような癖が続くと、奥歯に過度な力が加わり、歯の摩耗や破折の原因となります。また、顎の筋肉にも負担がかかり、顎関節症のリスクが高まります。日中でも、集中しているときやストレスを感じているときに無意識に歯を食いしばることがあり、これが慢性的な問題へと発展することもあります。
歯ぎしりによる歯や顎へのダメージと改善策
歯ぎしりは、歯の表面をすり減らし、知覚過敏や歯の破折を引き起こすことがあります。また、顎の筋肉や関節にも影響を及ぼし、顎関節症の原因となることもあります。改善策としては、マウスピースの使用や、ストレスの軽減、生活習慣の見直しなどが挙げられます。しかし、これらの方法でも改善が見られない場合、ボトックス治療を検討するケースもあります。
ボトックス治療の基礎知識

ボトックス治療は、美容目的だけでなく、医療分野でも広く利用されています。特に、食いしばりや歯ぎしりの症状の軽減が期待されています。ここでは、ボトックス治療の基本的な知識について解説します。
ボツリヌス製剤とは?治療に使われる成分を解説
ボツリヌス製剤は、ボツリヌス菌から抽出されたタンパク質で、筋肉の過剰な収縮を抑制する働きがあります。この製剤を特定の筋肉に注射することで、筋肉の緊張を緩和し、さまざまな症状の改善が期待できます。歯科領域では、咬筋や側頭筋など、食いしばりや歯ぎしりに関与する筋肉への注射が行われます。
咬筋への「注射」による筋肉の働きの抑制メカニズム
咬筋は、噛む動作に関与する主要な筋肉の一つです。この筋肉にボツリヌス製剤を注射することで、神経伝達物質の放出が抑制され、筋肉の収縮が緩和されます。その結果、食いしばりや歯ぎしりの頻度や強度が減少し、歯や顎への負担が軽減されます。効果は通常、数日から2週間で現れ、4〜6ヶ月程度持続します。
歯科で行うボトックス治療の特徴
歯科でのボトックス治療は、主に食いしばりや歯ぎしりの改善を目的としています。一方、美容目的でのボトックス治療は、しわの改善や小顔効果を狙ったものです。使用する部位や目的が異なるため、治療を受ける際は、目的に応じた専門医に相談することが大切です。
ボトックス治療のメリット

食いしばりや歯ぎしりに悩む方にとって、ボトックス治療は単なる対策ではなく、生活の質そのものを高めるきっかけになることがあります。マウスピースが合わず悩んでいる方にもおすすめできる選択肢です。ここでは、具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
筋肉の緊張緩和による食いしばりの「改善」が期待できる理由
食いしばりや歯ぎしりは、無意識のうちに咬筋や側頭筋などの筋肉が過剰に働くことで発生します。この状態が続くと、歯の摩耗や破折、さらに顎関節症のリスクが高まります。ボトックス治療では、咬筋に直接ボツリヌス製剤を注射し、筋肉の過度な緊張を緩和します。この働きによって、食いしばりの習慣が和らぎ、顎や歯への負担が大幅に軽減されるのです。
また、筋肉の緊張がほぐれることで血流が改善し、肩や頭の違和感が軽減されると感じる方もいます。特に睡眠中に無意識に歯を食いしばる方は、朝起きたときの顎のだるさや痛みが減少することを実感しやすいでしょう。
さらに、咬筋が緩むことで顔のラインにも変化が現れ、小顔への変化を実感される方もいます。これは、美容外科でのエラボトックス治療にも通じる効果で、信頼性の高い製剤 を使用することで、より自然な仕上がりを実現できます。
マウスピースが合わない方への治療選択肢
マウスピースは歯ぎしりや食いしばりの予防に広く用いられていますが、すべての人に適しているわけではありません。寝ている間に違和感で目が覚めてしまう、口に異物が入ることで無呼吸のような状態になってしまうなどのデメリットを感じる方も多いです。
また、矯正中の方や前歯に負担がかかる方の場合、マウスピースがしっかりフィットせず、逆に歯や歯茎への圧迫感が増してしまうケースもあります。その場合、ボトックス治療は装置を使用せずに自然な形で症状改善を目指せます。
特に忙しく都心部で働く方にとっては、短時間で治療が完了し、翌日から通常の生活に戻れる点も大きなメリットです。ボトックス治療は一度の注射で数ヶ月の効果が期待できるため、頻繁に歯医者に通う時間が取れない方にも適しています。
奥歯や顎への過剰な負担軽減と歯の健康維持
強い食いしばりは奥歯に過度な負担をかけ、歯の摩耗だけでなく、歯周病や歯槽膿漏の進行にもつながりかねません。ボトックス治療は、歯の負担軽減が期待できます。また、無意識に歯を食いしばる癖は顎関節に強い負荷をかけ、痛みや開口障害といった顎関節症の症状を引き起こすことがあります。ボトックスによって咬筋や側頭筋の過緊張を抑制することで、顎関節への負担が軽減され、症状の悪化を防ぐことができるでしょう。
さらに、奥歯やこめかみ周辺の筋肉の負担が減ることで、顔全体のたるみ予防にもつながり、美容面での効果を実感する方も少なくありません。このように、ボトックス治療は単なる食いしばり対策にとどまらず、歯と身体全体の健康維持、美容面でのメリットまで兼ね備えた治療法といえます。
ボトックス治療のリスクとデメリット
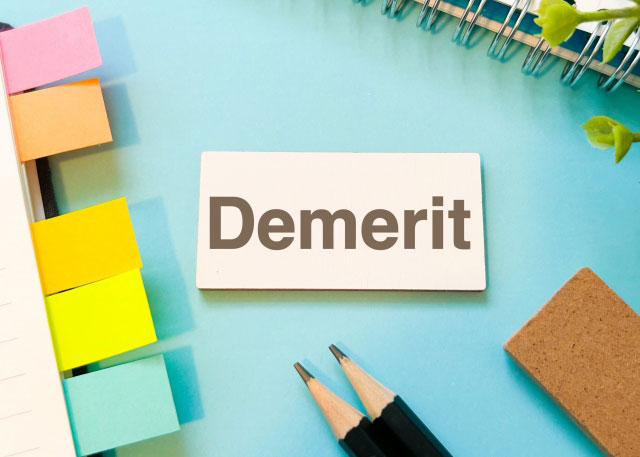
ボトックス治療は多くのメリットがありますが、医療行為である以上、リスクやデメリットも理解しておく必要があります。治療を受ける前にこれらを正しく把握することで、より安心して適切な対策が取れるでしょう。ここからは具体的なリスクとその対策について見ていきましょう。
一時的な副作用と考えられる症状
ボトックス治療では、一時的な副作用が現れる場合があります。注射部位の腫れや赤み、軽い痛み、内出血などが代表的な症状です。通常、数日から1週間ほどで自然に改善しますが、体質によっては症状が長引くこともあります。その際は、歯科医師に相談することが大切です。
また、筋肉の動きを一時的に抑制する性質上、噛む力が弱まることがあり、硬いものを噛む際に違和感を覚えることがあります。特に長時間の会話や食事時には、顎の疲れを感じやすくなるかもしれません。ただし、これらの症状は効果が現れている証拠でもあり、時間の経過とともに自然に回復します。
施術後は注射部位への強い刺激やマッサージは避けるべきです。適切なアフターケアを行うことで、こうした副作用のリスクは最小限に抑えられます。
「効果」の持続期間と定期的な再「注射」の必要性
ボトックス治療の効果は永久的ではありません。一般的に持続期間は3〜6ヶ月程度とされており、使用するボツリヌス製剤の種類や注入量、個人の代謝によっても差があります。特に高品質な製剤は持続性に優れることで知られていますが、それでも一定の期間を過ぎると効果は薄れていきます。
このため、効果を持続させるには定期的な再注射が必要になります。一般的には年2〜3回程度の施術が推奨されており、生活習慣や症状の強さに応じて通院回数は変動します。費用面では自由診療となるため保険は適用されませんが、症状によっては医療費控除の対象になる場合があります。治療を始める前に、料金や期間、継続的な費用について十分に相談することが重要です。
妊娠中・授乳中のリスクと治療制限
妊娠中や授乳中は、体が非常にデリケートな状態にあります。この時期にボツリヌス製剤を使用することは、胎児や乳児への影響が十分に解明されていないため、一般的には推奨されていません。特に妊娠初期は、母体の状態が胎児に大きな影響を及ぼすため、すべての医療行為に慎重さが求められます。
万が一、妊娠が判明した場合は、速やかに治療を中止し、必ず医師に相談してください。また、授乳中も同様にボツリヌス製剤が母乳を通じて乳児に影響を与える可能性が完全には否定できないため、安全を最優先に考え、治療は控えたほうが良いでしょう。
ボトックス治療の「料金」と「費用」相場

ボトックス治療は自由診療のため、治療にかかる料金は医療機関によって異なります。事前にしっかりと確認し、納得したうえで治療を受けることが大切です。ここでは、一般的な費用感について紹介します。
自由診療における治療「料金」の目安
食いしばりや歯ぎしり改善を目的としたボトックス治療では、1回の注射につき3万〜8万円程度が相場です。使用する製剤の種類や注射する部位、施術するクリニックの所在地(東京や銀座などの都市部か地方か)によっても大きく異なります。信頼性のある製剤を使用する場合は、やや料金が高くなる傾向にあります。
施術回数は一般的に年に2〜3回程度必要とされ、その分費用も継続的に発生します。料金に関する詳細は事前に必ず確認し、納得できるクリニックを選ぶことが重要です。
医療費控除の対象になる場合とは
ボトックス治療は自由診療ですが、症状の改善を目的とした場合には医療費控除の対象となることがあります。例えば、顎関節症や慢性的な歯ぎしりによる歯の損傷を防ぐための治療であれば、税務署に申告することで一定の税金還付が受けられる場合がありますので、詳細は専門機関にご相談ください。
ただし、美容目的で行う小顔やエラボトックス治療は医療費控除の対象にはなりません。申告時には、領収書を保管しておくこと、治療目的を明記した証明書を医療機関に発行してもらうことが必要です。
マウスピース治療との比較

食いしばりや歯ぎしりの改善には、従来からマウスピース治療が広く行われてきました。しかし、近年ではボトックス治療も新たな選択肢として注目されています。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。それでは、具体的に比較していきましょう。
マウスピースとボトックス、それぞれの「メリット」と「リスク」
マウスピースは、寝ている間に装着することで歯ぎしりによる歯の摩耗や破折を防ぎます。物理的な保護ができることが最大のメリットですが、装着時に違和感を覚えたり、無呼吸のような症状を引き起こすリスクもあります。特に矯正中の方や前歯に圧力がかかりやすい方は、装着が難しい場合もあります。
一方、ボトックス治療は注射によって筋肉の過剰な働きを抑えることで、根本的に食いしばりの癖を改善へと導きます。マウスピースのように装着の手間がなく、日常生活への影響も少ないのが利点です。しかし、効果は一時的であり、定期的な再注射が必要になる点は考慮すべきリスクです。
組み合わせて行う予防的アプローチ
マウスピースとボトックス治療は、それぞれ単独でも効果がありますが、組み合わせて行うことでより高い改善効果が期待できます。ボトックスで筋肉の緊張を緩和しつつ、マウスピースで物理的な保護を行うことで、歯や顎への負担を最小限に抑えられます。
特に重度の食いしばりや歯ぎしりに悩む方は、両方の治療を併用することで、睡眠中の無意識な行動によるダメージを大きく軽減できます。歯科医師とよく相談し、自分に適したアプローチを選びましょう。
治療後の注意点とアフターケア

ボトックス治療後は、適切なアフターケアを行うことで、副作用のリスクを減らし、効果を長く持続させることができます。ここでは、治療後に注意すべきポイントをご紹介します。
「注射」部位のケアと日常生活で注意すべきこと
治療直後は、注射部位を強く押さえたり、マッサージを行うのは避けてください。血流が促進されすぎることで、薬剤が意図しない部位に拡散してしまうリスクがあります。また、当日は激しい運動や入浴を控え、アルコールの摂取も避けた方が安心です。
睡眠時の姿勢にも注意し、枕の高さを調整するなどして、顎や首に過度な負担がかからないよう心がけましょう。これにより、治療後の痛みや違和感を最小限に抑えられます。
再発予防のための生活習慣改善と「癖」の見直し
ボトックス治療は一時的に症状を和らげる手段ですが、長期的な改善には生活習慣の見直しが不可欠です。特にストレスは食いしばりや歯ぎしりの大きな原因となるため、リラクゼーション法を取り入れたり、十分な睡眠を確保することが重要です。
また、日中の無意識な癖に気付くことも大切です。歯を食いしばっていないか定期的に意識し、顎の力を抜く習慣をつけましょう。オフィスワークでの長時間の同じ姿勢は肩こりや顎への負担にもつながるため、こまめに姿勢を正すことも予防につながります。
よくある質問(Q&A)

ここでは、ボトックス治療に関してよくある質問にお答えします。治療を検討している方はぜひ参考にしてください。
ボトックス「治療」の「効果」はどれくらいで実感できる?
効果は通常、注射から数日〜2週間程度で現れます。個人差はありますが、筋肉の緊張が和らぎ、朝の顎のだるさや痛みが軽減されたと実感する方が多いです。最大の効果は1ヶ月程度で現れ、持続期間は3〜6ヶ月程度が一般的です。
「改善」にはどのくらいの頻度で通院が必要?
効果を維持するためには、年に2〜3回の施術が目安となります。ただし、症状の強さやライフスタイルによっても必要な回数は異なるため、歯科医師と相談しながら無理のないスケジュールで通院することをおすすめします。
「マウスピース」や他の治療法との併用は可能?
はい、併用は可能です。むしろ、ボトックス治療とマウスピースを併用することで、食いしばりや歯ぎしりの予防効果はより高まります。それぞれの治療法のメリットを活かしながら、効果的に症状の改善を目指しましょう。
まとめ
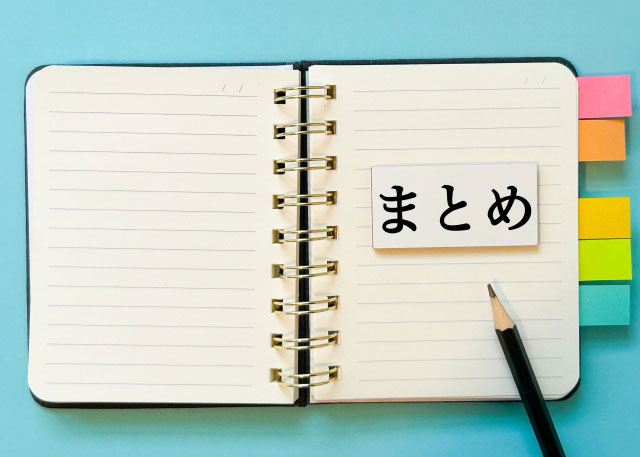
食いしばりや歯ぎしりは、歯や顎に大きな負担をかけるだけでなく、慢性的な肩こりや頭痛、美容面でのたるみといった問題にもつながります。こうした問題を改善するためには、マウスピースやボトックス治療といった適切な対策が必要です。
特に、マウスピースが合わない方や、長期間にわたる改善を目指したい方には、ボトックス治療は非常に有効な選択肢といえるでしょう。信頼性の高い製剤を使用し、専門家に相談することで、より安心して治療を進められます。
一方で、妊娠中・授乳中の方や副作用のリスクを十分に理解した上での判断も重要です。自分の症状や生活環境に合わせた最適な治療法を見つけ、生活の質を向上させましょう。
関連ページ
この記事の監修
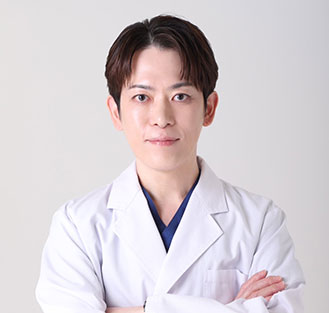
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463