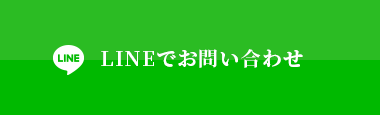目頭切開の抜糸は何日後?二重整形後の痛み・麻酔・ダウンタイムを徹底解説

症例ピックアップ
目頭切開の抜糸とは?基本の流れと方法を解説
目頭切開の抜糸とは、手術後に使用された縫合糸を取り除く処置を指します。この工程は、手術の一環として重要であり、回復過程において欠かせないステップです。抜糸の方法やタイミングは、個人の回復状況や医師の判断によって異なりますが、一般的には数日から一週間程度で行われることが多いです。抜糸の際には、麻酔の使用や痛みの程度についても考慮され、患者の快適さが重視されます。また、抜糸後のケアやメイクの再開時期についても、医師の指導に従うことが大切です。
抜糸とはどんな処置?
抜糸とは、手術後に使用された縫合糸を取り除く医療行為です。この処置は、傷口の治癒過程において重要なステップであり、感染リスクを抑えるために適切なタイミングで行われます。抜糸の方法や時期は、手術の種類や個人の回復状況によって異なりますが、一般的には手術後数日から一週間程度で行われることが多いです。処置中の痛みや不快感を軽減するために、局所麻酔を使用する場合もあります。抜糸後は、傷口のケアや日常生活での注意点について、医師の指導に従うことが重要です。
抜糸の方法と施術後の注意点
抜糸の方法は、手術で使用された縫合糸の種類や部位によって異なります。一般的には、医師が専用の器具を用いて、縫合糸を丁寧に取り除きます。処置中の痛みを軽減するために、局所麻酔を使用することもあります。抜糸後は、傷口の清潔を保ち、感染を防ぐためのケアが必要です。また、抜糸直後は腫れや赤みが生じることがありますが、これらは通常数日で軽減します。医師の指導に従い、適切なスキンケアやメイクの再開時期を守ることが、スムーズな回復につながります。
抜糸前・抜糸後で変わる見た目の違い
抜糸前は、縫合糸が残っているため、傷口が目立ちやすく、腫れや赤みが見られることがあります。また、洗顔やメイクに制限があるため、見た目に影響を与えることもあります。一方、抜糸後は、縫合糸が取り除かれることで、傷口の見た目が改善され、腫れや赤みも徐々に軽減します。メイクの再開が可能になることで、見た目の印象も向上します。ただし、抜糸後も完全な回復には時間がかかるため、医師の指導に従い、適切なケアを継続することが重要です。
目頭切開の抜糸は何日後?期間の目安と理由

目頭切開の抜糸は、一般的に手術後5日から7日目に行われることが多いです。この期間は、傷口がある程度治癒し、縫合糸を取り除くのに適したタイミングとされています。ただし、個人の回復状況や手術の内容によって、抜糸の時期は前後することがあります。医師の判断に従い、最適なタイミングで抜糸を行うことが、回復を早めるために重要です。
抜糸は何日目?一般的な目安と医師の判断
抜糸は、手術後5日から7日目に行われるのが一般的です。この時期は、傷口がある程度治癒し、縫合糸を取り除くのに適したタイミングとされています。ただし、個人の回復状況や手術の内容によって、抜糸の時期は前後することがあります。医師は、傷口の状態や腫れの程度を確認し、最適なタイミングで抜糸を行います。早すぎる抜糸は、傷口の開きや感染のリスクを高める可能性があるため、医師の判断に従うことが重要です。
抜糸が遅れるとどうなる?
抜糸のタイミングが遅れると、糸が皮膚と癒着しやすくなり、抜糸時の痛みが強くなる可能性があります。また、長く放置すると赤みや腫れが長引くこともあり、見た目に変化が現れることもあります。とくに、目頭切開の抜糸はデリケートな部位で行われるため、最短でも医師が問題ないと判断された日程内に行うことが推奨されます。抜糸直後の肌状態を良好に保つには、抜糸までの期間を守ることが重要です。抜糸はいつするかを自己判断せず、医師の診察に基づいて決めるようにしましょう。
抜糸前にできる準備とは
抜糸前には、スムーズな処置が行えるよう準備を整えておくと安心です。まず、抜糸予定の3日〜5日前からは刺激の強いスキンケアやメイクを控え、清潔な状態を保つようにします。洗顔もゴシゴシ擦らず、優しく行うことが大切です。抜糸当日は、目元にファンデーションやアイメイクをせず、すっぴんで来院するのが望ましいとされています。さらに、抜糸後に備えて冷却グッズや、医師から指示されたケア用品をあらかじめ用意しておくと、回復を早める助けになります。抜糸前に準備をしておくことで、安心して処置を受けられるでしょう。
抜糸は痛い?麻酔はする?実際の体験談と対策

目頭切開の抜糸は痛いかどうか、多くの人が不安に感じる部分です。実際には、痛みの感じ方は個人差があり、「チクッとする程度だった」という声もあれば、「少し涙が出た」という人もいます。局所麻酔を使うこともありますが、通常は必要ないとされることも多く、その判断は医師によって異なります。抜糸の痛みを軽減するためには、術前からの適切なケアと、抜糸までの肌状態の維持が大切です。処置は早ければ4日で抜糸を終えるケースもありますが、一般的には5日目から6日目が目安とされます。
抜糸の痛みの程度と個人差
抜糸の痛みは人それぞれであり、「まったく痛くなかった」と話す人もいれば、「涙が出た」と感じる人もいます。目頭の皮膚は薄いため、少しの刺激でも敏感に反応しやすい部位です。そのため、抜糸直後の違和感やチクチクした痛みは避けられない場合があります。痛みを少しでも早める方法としては、抜糸前の肌を清潔に保ち、過度なメイクや洗顔を控えることが有効です。多くの美容外科では痛みの軽減にも配慮されており、必要に応じて局所麻酔が使用されることもあります。
麻酔の有無と不安な人への対応方法
目頭切開の抜糸時に麻酔が使われるかどうかは、クリニックの方針や患者の希望によって異なります。通常は、痛みが我慢できる程度であるため麻酔なしで行われることが多いですが、不安が強い場合には事前に相談することで局所麻酔を使用してもらえることもあります。麻酔を使うと感覚が鈍くなるため、抜糸中の不快感はほとんどありません。多くの美容外科では、患者の安心感を重視した対応が一般的で、処置前には丁寧な説明がされることが多くあります。不安を感じたまま施術を受けるのではなく、カウンセリング時にしっかり質問をすることが大切です。
痛みを軽減するためにできること
抜糸の痛みを少しでも軽くするためには、抜糸までの数日間の過ごし方が重要です。術後3日〜5日は特に敏感な時期であるため、目元を強く触れたり、洗顔時に擦ったりしないよう注意が必要です。また、メイクもできるだけ控え、肌への刺激を避けることで、回復がスムーズになります。抜糸当日は、患部が清潔な状態であるほど処置も早く終わり、痛みを最小限に抑えられることがあります。冷却ジェルや処方された塗り薬を活用することも、痛みを和らげる助けになります。
抜糸前の生活は?仕事やメイクはできる?

目頭切開の抜糸までの期間中は、日常生活にいくつかの制限があります。特に気をつけたいのが、仕事復帰のタイミングやメイクの使用、洗顔の方法です。手術後3日〜4日は腫れや赤みが強く出やすいため、仕事への復帰は5日目以降が無理のないタイミングとされています。また、抜糸前は目元の傷口が繊細な状態であるため、メイクは避けた方が安全です。洗顔も優しく行い、泡でそっと洗い流すようにしましょう。抜糸までの数日間は、腫れを早めに引かせるためにも安静に過ごすことが望まれます。
抜糸前の仕事復帰タイミングと注意点
仕事への復帰時期は、目頭切開の抜糸が完了する前でも可能ですが、術後3日〜5日は腫れや内出血が残ることがあります。そのため、デスクワークなど軽度な業務であれば4日で抜糸前でも復帰が可能とされますが、人前に出る職業の場合は見た目に配慮して5日目以降が良いとされています。また、パソコン作業などで目を酷使すると腫れが長引く可能性もあるため、なるべく画面を見る時間を短縮するなどの工夫も大切です。抜糸までの期間中は、目を守る意味でもサングラスや伊達メガネで外出時の刺激から保護するのが安心です。
抜糸前にメイクしてもいい?NG行動を解説
抜糸前の期間中は、目元の皮膚が非常に敏感な状態になっているため、メイクは基本的に控えるべきです。特にアイシャドウやアイライナー、マスカラなどは刺激が強く、化粧品の成分が傷口に触れると炎症を引き起こす恐れがあります。また、クレンジングの際に擦ってしまうことで腫れや赤みが悪化する可能性もあるため注意が必要です。抜糸が完了するまでは、ベースメイクも目の周囲は避けるのが無難です。どうしてもカバーしたい場合は、医師に相談の上、使用可能な範囲を確認することをおすすめします。目頭切開の抜糸までは、肌をできるだけ休ませることが回復を早めるポイントです。
抜糸前にしておきたいスキンケア
抜糸前のスキンケアでは、清潔を保つことが最も大切です。洗顔はゴシゴシ擦らず、泡で包み込むようにやさしく行いましょう。また、洗顔料は低刺激で香料の少ないものを選ぶと安心です。化粧水や乳液を使用する際も、目元を避けて塗布することで、抜糸直後の腫れやトラブルを予防しやすくなります。日本国内の多くのクリニックでは、抜糸までの期間中に特別なスキンケア製品を推奨することもありますので、気になる場合は医師に確認しておくと良いでしょう。術後5日間のケア次第で、見た目の印象に影響する可能性があるため、丁寧な対応が求められます。
抜糸後の変化と注意点|腫れ・かさぶた・メイクのタイミング

目頭切開の抜糸直後は、見た目にさまざまな変化が表れます。多くの人が気にするのは腫れやかさぶたの状態ですが、これらは一時的なもので、早ければ3日〜4日程度で落ち着きます。抜糸が完了したからといってすぐに元通りの生活に戻れるわけではなく、特にメイクや洗顔には注意が必要です。抜糸後も皮膚は非常に繊細で、外部からの刺激に反応しやすいため、医師の指導に従ってケアを続けることが大切です。見た目の印象は抜糸後に大きく変わるため、回復期間は焦らず、ゆっくり過ごすことが大切です。
抜糸後に腫れはどれくらい続く?
抜糸後に残る腫れは個人差がありますが、一般的には3日〜5日ほどで落ち着いてくることが多いです。抜糸直後は一時的に腫れが強まったように感じる人もいますが、それは糸が取れたことで皮膚が自然な形に戻ろうとしている過程でもあります。目元は特にデリケートな部位であるため、抜糸後も無理に洗顔したり、強く触れたりするのは避けた方が安全です。腫れを早めに引かせるためには、就寝時に頭を少し高くして寝る、冷却をこまめに行うといった方法が役立ちます。腫れがなかなか引かない場合は、迷わず医師に相談しましょう。
抜糸後にかさぶたができたら?自然な剥がし方
抜糸後は小さなかさぶたができることがありますが、これは自然な治癒の一部です。無理に剥がそうとすると傷が開いたり、色素沈着の原因になることもあるため、自然に剥がれ落ちるのを待つのが基本です。かさぶたは洗顔や入浴の際に自然にふやけて取れることが多いので、触れずに清潔を保つことが最善の方法です。日本のクリニックでも、かさぶたの扱いについては特に注意点として説明されることがあり、抜糸後はより慎重なケアが求められます。メイクもかさぶたが残っている間は控えることで炎症などを防げます。
抜糸後のメイクは何日後からOK?注意すべき点とは
抜糸後のメイク再開は、腫れや赤みの引き具合に応じて判断されますが、一般的には抜糸から2日〜3日ほど経過し、傷口が落ち着いてからが目安です。ただし、アイメイクはとくに刺激が強いため、5日目以降まで控えることが推奨される場合もあります。使用する化粧品はなるべく低刺激でクレンジングしやすいものを選び、メイク後の洗顔では目元をこすらないよう注意しましょう。二重のラインが完成に向かう段階では、あまり強く触れずに自然な回復を優先することが、理想的な仕上がりにつながります。
二重整形後のダウンタイムと回復期間の目安

目頭切開と同時に行われることの多い二重整形では、術後のダウンタイムをどう過ごすかが仕上がりに影響します。特に抜糸までの期間や、その後の腫れの引き具合が見た目に大きく関係します。一般的には、3日目から腫れが落ち着き始め、5日〜6日目には日常生活に戻れる程度まで回復することが多いです。メイクの再開や洗顔のタイミングについても、医師の指示を守ることが求められます。早めに回復させたい場合は、冷却や安静を意識し、無理に普段の生活に戻ろうとしないことが大切です。回復には個人差があるため、焦らず慎重に過ごすことがポイントです。
抜糸後の経過と二重の仕上がりの変化
抜糸直後は、まだ腫れや赤みが残っている場合がありますが、日が経つごとに落ち着いていきます。5日目から6日目あたりになると、腫れも少なくなり、二重のラインがはっきり見え始めます。ただし、この段階でも見た目は完成形ではありません。二重の最終的な仕上がりは、個人差があるものの、1か月前後で自然な状態に整うとされています。抜糸後にすぐメイクを再開したい気持ちは分かりますが、早い段階での刺激は仕上がりに影響する可能性があるため注意が必要です。医師の説明をよく聞いて、適切な期間を設けましょう。
ダウンタイム中の過ごし方と注意事項
ダウンタイム中は、回復を助けるためにも静かに過ごすことが基本です。術後3日〜5日は特に腫れが目立つことが多いため、外出は控え、自宅で目元を冷やすなどのケアを行うのが理想的です。また、洗顔やメイクは抜糸まで避けるのが安全であり、強い摩擦を与える行為は控えるべきです。スマートフォンやパソコンの長時間使用も、目の疲労を招いて腫れを悪化させる原因になります。日本の美容クリニックでは、ダウンタイムの過ごし方について詳しい説明がなされることが多く、それを参考にすると安心して過ごせます。落ち着いた生活が、回復を最短で迎えるカギとなります。
回復期間を短くするためのコツと対策
目頭切開と二重整形の回復期間を早めたい場合、術後の過ごし方が非常に重要です。抜糸までの期間中はとくに肌に触れる機会を減らし、腫れを抑えるための冷却や睡眠環境の調整が効果的です。就寝時に頭を高くして寝ることで、むくみを軽減できます。抜糸後すぐに洗顔やメイクを再開したくなる気持ちはありますが、刺激を避けることで仕上がりが美しく保たれます。また、栄養バランスの良い食事や水分補給も、回復力を高める要素になります。医師の指示通りに過ごし、仕上がりを理想に近づけるための参考にしてください。
まとめ

目頭切開の抜糸は、術後の見た目や回復に大きく関わる重要な工程です。一般的には5日目〜6日目に行われることが多く、抜糸直後には腫れや赤みが残ることもありますが、正しくケアすることで早く落ち着いていきます。抜糸まではメイクや洗顔に制限があるため、あらかじめ準備を整え、医師の指示に従うことが大切です。抜糸が痛いと感じるかどうかには個人差があり、場合によっては麻酔を使う選択もあります。二重整形とあわせて行われる場合も多いため、ダウンタイム中の過ごし方や回復期間を意識しながら、最短で理想的な仕上がりを目指すことが大切です。施術から抜糸までの流れを理解しておけば、施術を受ける際に安心できます。
関連ページ
この記事の監修
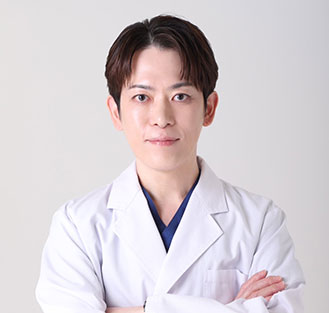
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463