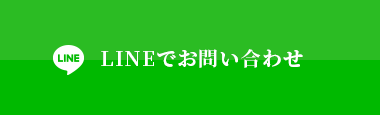防已黄耆湯の効果とは?多汗症や痩せる作用・気になる副作用を解説

防已黄耆湯に期待できる2つの主な効果
防已黄耆湯は、東洋医学の観点から「水分代謝の異常」とエネルギーである「気」の不足に関連する症状に効果を発揮する漢方薬です。
そのため、具体的な効果としては、汗のコントロールに関する悩みと、体内の余分な水分によって引き起こされるむくみの改善という、2つの主要な作用が期待できます。
【多汗症への効果】汗の量を調節し肌のバリア機能を高める
漢方では、体の表面を覆って外部の刺激から守り、汗腺の開閉を調節する「衛気(えき)」というエネルギーが存在すると考えられています。
体力が低下してこの衛気が不足すると、汗腺のコントロールがうまくいかなくなり、必要以上に汗をかく多汗の状態になるとされます。
防已黄耆湯に含まれる黄耆には、この衛気を補い体表を引き締める作用があるため、汗の量を正常に調節する効果が期待できます。
また、衛気は肌のバリア機能も担っており、この機能を高めることで、汗による肌トラブルの予防にもつながります。
特に、じっとしていても汗が漏れ出るような自汗症の改善に適した処方です。
【ダイエット効果】余分な水分を排出しむくみを改善する
防已黄耆湯がダイエットに用いられるのは、脂肪を直接燃焼させるのではなく、主に水分代謝を改善する作用によります。
この漢方薬は、胃腸の働きを助けて体内の水分バランスを整え、余分な水分を尿として排出させる利尿作用を持ちます。
この働きにより、むくみが解消され、体がすっきりすることで「痩せた」と感じられるのです。
特に、食事量は多くないのに太りやすい、体が重だるいといった「水太り」タイプの肥満症に適しています。
水分代謝が正常化することで、体重減少や見た目の変化だけでなく、体が軽くなる感覚を得られる場合もあります。
防已黄耆湯の効果を実感しやすい人の特徴

漢方薬は、その人の体質や症状に合っているかが効果を得るうえで重要です。
防已黄耆湯は、特に体力がなく疲れやすい「虚証」と呼ばれるタイプの人に向いているとされます。
そのため、体力がある人には効果が出にくい場合があります。
また、更年期に見られるむくみや多汗といった、ホルモンバランスの変化に伴う不調の緩和に用いられることもあります。
疲れやすく体力に自信がない人
防已黄耆湯は、体力が充実している人よりも、虚弱体質で疲れやすい人に適した処方です。
具体的には、少し動いただけですぐに息切れがする、日常的にだるさを感じやすい、気力がわかないといった「気虚(ききょ)」の状態にある人が対象となります。
汗をかくこと自体が体力を消耗させるため、多汗によってさらに疲れやすくなるという悪循環に陥っている場合にも向いています。
夏バテしやすく、食欲が落ちてしまうような、エネルギーが不足しがちな体質の人には、気を補いながら水分代謝を整えるこの漢方薬の効果が期待できます。
体力に自信がない人の体調管理に役立ちます。
色白で筋肉が柔らかい水太りタイプの人
この漢方薬が特に適しているのは、いわゆる水太りタイプの人です。
外見的な特徴としては、肌の色が白く、血色があまり良くない点が挙げられます。
また、筋肉質ではなく、全体的に体に締まりがなく、触ると柔らかい感触があるのも特徴です。
運動不足で筋肉量が少なく、基礎代謝が低い傾向にあるため、体内に水分を溜め込みやすくなっています。
夕方になると足がむくんで靴がきつくなる、朝に顔やまぶたが腫れぼったいなどの自覚症状がある場合が多いです。
このような体質で体重が増加傾向にある場合に、防已黄耆湯は水分の排出を促し、症状を改善する助けとなります。
膝の痛みや関節に水がたまりやすい人
防已黄耆湯は、変形性膝関節症など、関節の痛みの治療にも用いられます。
特に、炎症による強い熱や赤みを伴う痛みではなく、関節に水がたまって腫れぼったく、重だるいような痛みに効果的です。
これは、体内の水分代謝が悪化し、余分な水分が関節に溜まってしまうことが原因の一つと考えられるためです。
防已黄耆湯の利水作用によって、関節に溜まった余分な水分を排出し、腫れや痛みを和らげる効果が期待されます。
特に中高年以降の女性で、膝に水がたまりやすい、天気が悪いと関節が痛むといった症状を持つ人に適しています。
防已黄耆湯を服用する前に知っておきたい副作用

防已黄耆湯は比較的副作用が少ない漢方薬とされていますが、体質に合わない場合や、まれに重篤な副作用が起こる可能性もあります。
服用しても効果が効かないと感じるだけでなく、何らかの不調が現れた場合は、薬が合わないサインかもしれません。
安全に使用するためにも、事前に副作用について理解しておくことが重要です。
偽アルドステロン症の初期症状に注意する
防已黄耆湯に含まれる甘草(カンゾウ)という生薬の作用により、まれに「偽アルドステロン症」という副作用が起こることがあります。
これは、体内のホルモンバランスが崩れ、体にカリウムが不足し、ナトリウムと水分が溜まってしまう状態です。
初期症状として、手足のだるさ、しびれ、つっぱり感、こわばり、力の入りにくさ、筋肉痛などが現れます。
また、むくみや体重の増加、血圧の上昇(高血圧)といった症状もみられます。
これらの症状は防已黄耆湯の本来の効果と見分けがつきにくい場合があるため、特に注意が必要です。
気になる症状が現れた際は、直ちに服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
胃の不快感や食欲不振が起こる場合がある
防已黄耆湯の服用により、消化器系の副作用として、食欲不振、胃の不快感、吐き気、嘔吐、下痢などが生じることがあります。
これは、配合されている生薬が胃腸に負担をかけることで起こると考えられ、もともと胃腸が弱い人は症状が出やすい傾向にあります。
これらの症状は、ダイエット目的の食欲抑制とは異なり、体調不良のサインです。
不眠との直接的な因果関係は報告されていませんが、胃腸の不快感が睡眠の質に影響を及ぼす可能性は考えられます。
症状が続く場合は、服用を中止して専門家に相談することが推奨されます。
発疹やかゆみなどの皮膚症状が現れることがある
防已黄耆湯の成分に対してアレルギー反応が起こり、皮膚に副作用が現れる場合があります。
具体的には、発疹、発赤、かゆみなどの症状が報告されており、これらは薬が体質に合っていない可能性を示すサインです。
漢方薬は天然の生薬から作られているため、特定の植物にアレルギーを持つ人は注意が必要です。
服用を開始してから皮膚に異常を感じた場合は、すぐに服用を中止し、医師または薬剤師に相談することが重要です。
自己判断で服用を続けると症状が悪化する恐れがあるため、速やかな対応が求められます。
防已黄耆湯の効果的な飲み方とよくある質問

防已黄耆湯の効果を最大限に引き出すためには、適切な飲み方を理解しておくことが大切です。
効果を実感できるまでの期間や飲むタイミングは、薬の効果に影響を与える要素の一つです。
ここでは、服用にあたってのよくある質問について解説しますので、市販薬と処方薬の違いなども含めて参考にしてください。
効果を実感できるまでの期間はどれくらい?
防已黄耆湯は、体質を根本から改善していく漢方薬であるため、効果を実感できるまでにはある程度の時間が必要です。
症状や体質による個人差が大きいですが、一般的にはまず2週間から1ヶ月程度、毎日継続して服用することが推奨されます。
早い人では数週間でむくみが軽くなるなどの変化を感じることもありますが、多くの場合、効果は緩やかに現れます。
1ヶ月服用しても全く変化が見られない、あるいは症状が悪化するようであれば、薬が体質に合っていない可能性も考えられます。
その場合は自己判断で続けず、処方した医師や薬剤師に相談し、処方の見直しを検討してください。
いつ飲むのがベストなタイミング?
漢方薬は、一般的に食事の影響を受けにくい空腹時に服用することで、有効成分の吸収が良くなると考えられています。
そのため、食前(食事の30分~1時間前)または食間(食事と食事の間で、食後2時間程度が目安)に水または白湯で服用するのが最も効果的です。
ただし、胃腸が弱く、空腹時の服用で胃もたれなどを感じる場合は、食後に服用しても問題ありません。
医療用漢方製剤の場合、例えばツムラの防已黄耆湯エキス顆粒は、通常、成人1日7.5gを2~3回に分割して服用するよう指示されます。
飲み忘れないように、自分の生活リズムに合わせて服用時間を決めることが継続の鍵です。
市販薬と処方薬に違いはある?
防已黄耆湯は、医師の診断に基づいて処方される医療用医薬品と、ドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品(市販薬)の2種類があります。
両者の主な違いは、有効成分の含有量です。
一般的に、医療用の方が市販薬よりも多くの有効成分を含んでいるため、より高い効果が期待できます。
市販薬は、ツムラやクラシエといったメーカーから販売されており、手軽に購入できるメリットがありますが、まずは軽い症状から試したい場合に向いています。
どちらを選ぶべきか迷う場合は、医師や薬剤師に相談し、自分の症状や体質に合ったものを選択することが重要です。
多汗症や肥満に用いられる他の漢方薬や治療法

多汗症や肥満の悩みに対しては、防已黄耆湯以外にも様々な選択肢があります。
漢方では体質によって適した薬が異なり、西洋医学では別の角度からのアプローチが可能です。
例えば、気力を補う補中益気湯など他の漢方薬との併用を考える場合、成分の重複による副作用のリスクもあるため、自己判断せず必ず医師や薬剤師に相談が必要です。
【肥満】脂肪燃焼を促す防風通聖散との違い
肥満治療に用いられる漢方薬として有名なものに防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)がありますが、これは防已黄耆湯とは適応する体質が全く異なります。
防風通聖散は、体力が充実しており、お腹周りに皮下脂肪が多く、便秘がちな「実証」タイプの人向けです。
体の熱を冷まし、発汗や便通を促すことで余分なものを排出し、脂肪燃焼を促進する作用があります。
一方、防已黄耆湯は体力のない「虚証」タイプで、むくみによる水太りが主な症状の人向けとなります。
単に体重を減らす目的だけでなく、適度な運動を取り入れながら、自分の体質に合った漢方薬を選ぶことが重要です。
【多汗症】外用薬や内服薬による西洋医学の治療
多汗症の治療は漢方薬だけでなく、西洋医学的なアプローチも存在します。
一般的な治療法としては、まず塩化アルミニウム溶液などの外用薬(塗り薬)が用いられます。
これは汗腺にフタをすることで発汗を物理的に抑えるものです。
効果が不十分な場合は、アセチルコリンという発汗を促す神経伝達物質の働きをブロックする抗コリン薬などの内服薬が処方されることもあります。
局所的な多汗症には、ボツリヌス毒素の注射やイオントフォレーシスといった治療法も選択肢となります。
多汗症の原因は、ストレスやホルモンバランスの乱れなど多岐にわたるため、原因に応じた適切な治療法の選択が求められます。
まとめ
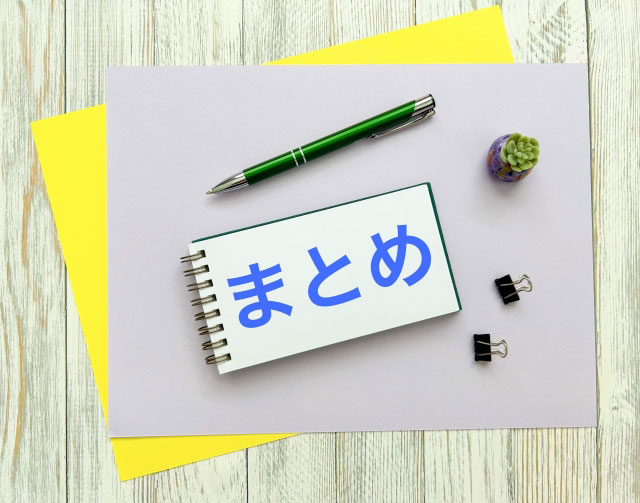
防已黄耆湯は、体力がなく疲れやすい人の水分代謝を改善する漢方薬です。
体内の余分な水分を排出する作用により、むくみが原因の肥満(水太り)や、関節の腫れや痛みを和らげる効果が期待されます。
また、体の表面のバリア機能を高めて汗の量を調節するため、多汗症の改善にも用いられます。
一方で、まれに偽アルドステロン症や胃腸症状、皮膚症状などの副作用が起こる可能性もあります。
服用中に異変を感じた場合はすぐに中止し、専門家に相談することが必要です。
自分の体質に適しているかを見極めるためにも、購入や服用の前には医師や薬剤師への相談が推奨されます。
関連ページ
提携クリニック
この記事の監修
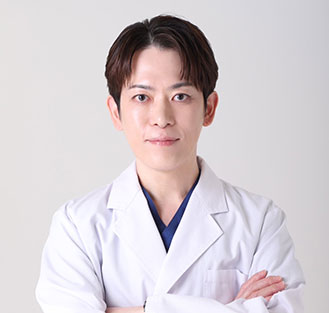
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463