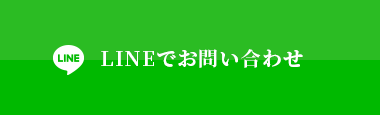GLP‑1受容体作動薬とは?薬の種類・作用・注意点をわかりやすく解説

GLP-1受容体作動薬とは?インクレチンとの違いや作用機序を解説
glp‑1受容体作動薬は、腸管ホルモンであるインクレチンのGLP‑1作用を模倣または強化する薬として、2型糖尿病治療や体重管理(ダイエット)領域で注目を集めています。
この種類の薬は、血糖値の調整、インスリン分泌促進、グルカゴン抑制、胃排出抑制といった複合的な働きを持ち、食欲抑制にもつながる効果を発揮します。
ここでは、まずインクレチンとの違い、GLP‑1受容体作動薬の作用機序、およびインスリンとの関係性について詳しく見ていきます。
GLP-1とインクレチンの関係とは?
インクレチンとは、食後に腸管から分泌されるホルモン群を指します。
その代表がGLP‑1で、これは膵β細胞を刺激してインスリン分泌を促す働きを持ち、さらに膵α細胞からのグルカゴン放出を抑制するホルモン機能を併せ持っています。
天然のGLP‑1は体内で速やかに分解され、作用時間が短いため、GLP‑1受容体作動薬はその持続性を改善するよう設計されたものです。
GLP-1受容体作動薬の作用機序とは
glp‑1受容体作動薬は、体内のGLP‑1受容体を活性化し、次のような複合的な作用を引き起こします。
まず、高血糖状態において、膵β細胞を刺激してインスリンの促進分泌を誘導します。
次に、膵α細胞からのグルカゴン分泌を抑え、肝臓からの糖放出を制御します。
また、胃排出を遅らせ、食後血糖のピークを抑えることで食欲抑制を助けます。
これらの作用を通じて、血糖値の変動幅を小さくしながら、体重抑制や減少に寄与します。
インスリンとの違いと関係性
インスリンはグルコースを細胞へ取り込ませる直接的なホルモン効果を持ちますが、glp‑1受容体作動薬はインスリンそのものではなく、インスリン分泌を促す補助的な役割を果たします。
重篤な糖尿病例では、この薬だけでは不十分なため、インスリン併用やインスリン合剤が採用されることがあります。
ただし、併用時には低血糖リスクが増大するため、慎重な調整とモニタリングが不可欠です。
GLP-1受容体作動薬の効果と副作用|糖尿病治療での役割

glp‑1受容体作動薬は、血糖値調整(HbA1c低下、空腹時血糖改善)と並行して、体重抑制や心血管保護といった効果を併せ持つ可能性が期待されます。しかし、副作用やリスクも存在するため、これらを正しく把握したうえで使用することが重要です。
2型糖尿病におけるGLP-1薬の効果とは?
2型糖尿病患者にglp‑1受容体作動薬を投与すると、血糖値の改善、HbA1cの低下、血糖値変動の安定化が見られます。
さらに、肥満を併発している例では、食欲抑制や体重変化を報告する例があります。
代表的な製剤には、セマグルチド(オゼンピック/リベルサス)、リラグルチド、トルリシティ、チルゼパチド(マンジャロ)などが含まれます。
リベルサスは3mg、7mg、14mgの用量を持ち、まず3mgの効果を確認してから増量する設計です。
他にも0.25mg、0.5mg、0.75mg、2.5mg、7.5mg、2.4mgなどの用量バリエーションを持つ製剤があり、週1回注射型・毎日注射型・内服型の選択肢があります。
代表的な副作用とリスク(マンジャロ・リラグルチドなど)
glp‑1受容体作動薬の副作用として最も頻度が高いのは胃腸症状、特に吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、便秘などです。
開始直後や用量調整期に現れやすく、通常は徐々に軽減することが多いです。
注射による副作用として注射部位反応(腫れ、発赤、痛み)も報告されます。
報告されている有害事象には、膵炎、胆石、腎機能変化、甲状腺変化、骨代謝への影響などがあります。慢性腎臓病や心不全の既往を持つ患者は特にリスク管理が必要です。glp‑1受容体作動薬の問題点として、長期的な安全性や未知のリスクも指摘され続けています。
副作用と糖尿病患者における注意点
糖尿病患者においてglp‑1受容体作動薬を導入する際は、他の糖尿病薬(特にインスリンやSU薬)との併用による低血糖リスクを慎重に評価する必要があります。
腎機能・肝機能低下例では薬の代謝・排泄が変動し、副作用発現頻度が変わる可能性があります。
膵炎既往、胆嚢疾患、甲状腺疾患、睡眠時無呼吸症候群、肥満症、胆嚢炎の機序に関連するリスク、脳・骨への影響などを持つ人は慎重投与または禁忌とされることがあります。
治療中は健康診断、血液検査、膵酵素・腎・肝機能モニタリングを定期的に行い、有害事象が疑われたら速やかに対応する必要があります。
GLP-1受容体作動薬の種類と一覧|注射と飲み薬の違いを比較
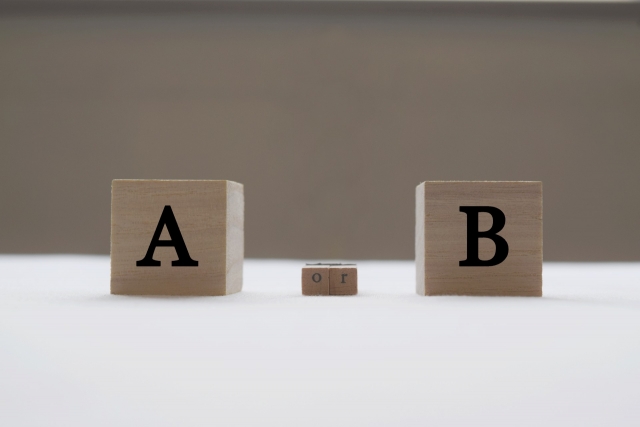
GLP-1受容体作動薬には、注射薬タイプと経口(飲み薬)タイプがあり、それぞれ作用の強さ、用量、投与頻度、副作用傾向などに違いがあります。本章では、それらの違いを整理し、代表的な製剤を一覧で比較します。
注射薬と飲み薬の違いとは?
注射薬は吸収効率や作用の安定性に優れており、週1回のタイプや毎日投与するタイプなどがあります。
一方、飲み薬(経口GLP-1受容体作動薬)は服用のしやすさが特長ですが、吸収率が影響を受けやすく、飲み方を守ることが非常に重要です。
たとえば、リベルサスのような経口薬では、起床後の空腹時に水で服用し、その後30分間は飲食や他の薬の摂取を避ける必要があります。
GLP-1受容体作動薬の代表的な薬の一覧
現在広く使用されているGLP-1受容体作動薬には、以下のような製剤があります。
- セマグルチド(注射:オゼンピック、経口:リベルサス)
- リラグルチド(ビクトーザ、サクセンダ)
- ドゥラグルチド(製品名:トルリシティ)
- チルゼパチド(マンジャロ)
- エキセナチド
- リキセナチド
これらの製剤は、ノボノルディスク、イーライリリー、サノフィなどの製薬会社によって開発・供給されています。
製薬企業と製剤名の関係
GLP-1受容体作動薬の開発を主導している製薬会社としては、ノボノルディスク(オゼンピック、リベルサスなど)や、イーライリリー(マンジャロなど)が挙げられます。これらの企業は、GLP-1製剤の新規開発や改良、作用時間の延長、利便性向上といった分野で積極的に研究を進めています。
飲み薬の種類とその効果(リベルサスなど)
リベルサスは、GLP-1受容体作動薬の中で初の経口剤として注目されています。3mg、7mg、14mgという用量があり、まず3mgから開始し、効果を見ながら段階的に増量します。服用は空腹時の起床直後に行い、服薬後30分間は飲食や他の薬の摂取を避ける必要があります。この服用ルールを守らないと、十分な効果が得られにくくなるため注意が必要です。
作動薬一覧:セマグルチド、リラグルチド、チルゼパチドなど
代表的なGLP-1受容体作動薬の有効成分には以下のようなものがあります。
- セマグルチド(注射・経口)
- リラグルチド(毎日注射)
- チルゼパチド(GLP-1とGIPのデュアル作動薬。高い体重減少効果で注目)
- ドゥラグルチド(週1回の注射型)
- エキセナチド
- リキセナチド
これらの成分ごとに作用の強さや持続時間、副作用リスクに違いがあるため、医師と相談のうえ、自分に適した薬剤を選ぶことが大切です。
GLP-1受容体作動薬ごとの特徴|マンジャロ・リベルサス・ウゴービなど
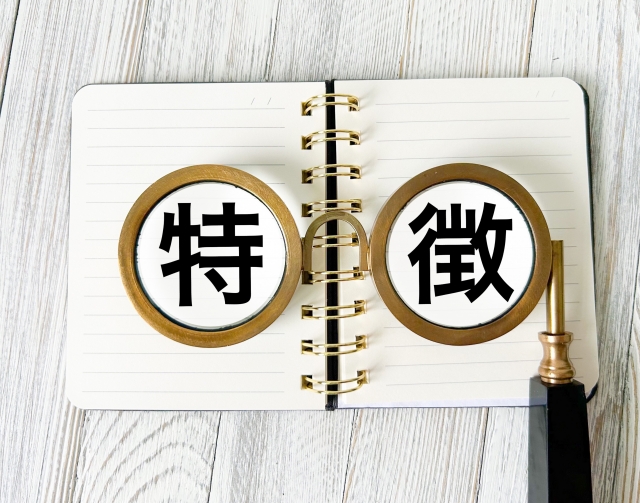
ここでは、現在注目されているGLP-1受容体作動薬の代表製剤について、それぞれの特徴、作用、副作用、服用・投与上の注意点をわかりやすく解説します。
マンジャロの特徴・作用・副作用とは?(チルゼパチド)
マンジャロ(チルゼパチド)は、GLP-1とGIPの両方の受容体に作用する「デュアルアゴニスト」です。GLP-1作動薬の中でも新しく、強力な体重減少効果と血糖コントロールが報告されており、特に肥満や2型糖尿病を併発している人に処方されることが多いです。
副作用としては、吐き気・嘔吐・下痢・便秘などの消化器症状に加え、まれに心不全の悪化・甲状腺機能変化・脳血管への影響・骨代謝への影響などが報告されています。週1回の注射型で、用量(0.25mg〜15mgまで)を段階的に増やしていくのが一般的です。
glp‑1受容体作動薬「マンジャロ」の位置づけ
マンジャロは、glp‑1受容体作動薬「マンジャロ」としても知られ、GLP‑1とGIPの複合作用を持つ配合剤として設計された製剤です。
その強い作用機序により、体重減少効果が優れるケースも報告されています。
商品名としても注目され、「glp‑1受容体作動薬一覧」に含まれる主要な候補の一つです。
リベルサスの効果と服用時のポイント
リベルサスは、セマグルチドを有効成分とする世界初の経口GLP-1受容体作動薬です。用量は3mg、7mg、14mgとあり、通常は3mgから開始し、効果に応じて増量していきます。
服用時の注意点としては、起床後すぐの空腹時に、水だけで服用し、その後30分間は飲食や他の薬の服用を避ける必要があります。このルールを守らないと吸収が著しく低下し、十分な効果が得られなくなります。利便性が高い反面、服用タイミングの管理がやや煩雑な点に注意が必要です。
ウゴービとは?肥満治療における注目薬
ウゴービは、GLP-1受容体作動薬として開発された、肥満症治療に特化した注射薬です。欧米では肥満症への適応で承認されており、日本国内でも臨床開発が進んでいます。
セマグルチドを高用量で用いることで体重減少効果が得られることが確認されており、今後、GLP-1製剤による「医療ダイエット」の中心的な存在になる可能性があります。
GLP-1受容体作動薬とインクレチンの違いを整理
GLP-1受容体作動薬は、インクレチン(特にGLP-1)という体内ホルモンの作用を模倣・強化する薬です。インクレチンは本来、食後に分泌されてインスリンを促す働きを持ちますが、体内での分解が非常に早いため、効果が長続きしません。
その欠点を補ったのがGLP-1受容体作動薬であり、長時間作用する構造を持たせることで、食欲の抑制、血糖コントロール、体重管理に活用できるようになっています。
費用・保険・使用時の注意点|生活習慣との関わりも重要

GLP-1受容体作動薬は医師の指導のもとで使用する薬であり、安全に・効果的に使うためには、費用や保険、生活習慣との連携、そして副作用管理までトータルに理解することが不可欠です。
薬の費用と保険適用の違いとは?
GLP-1受容体作動薬の価格は、注射型か内服型か、用量、投与頻度、製剤によって大きく異なります。日本国内では、2型糖尿病治療として処方される場合には保険が適用されることがありますが、ダイエット目的や高用量での使用は自由診療扱いとなり、全額自己負担になります。
自由診療では、月あたりの薬代・診察料・検査費用を含めて2万円〜5万円前後かかるケースもあります。事前に価格体系や継続のしやすさを確認しておくことが重要です。
生理周期や女性の服用に関する注意点
女性がGLP-1薬を使用する場合、生理周期や女性ホルモンの変動が薬の作用や副作用に影響する可能性があります。特に、吐き気や嘔吐といった消化器症状が出やすくなることがあるため、月経前後の体調変化に注意が必要です。
また、妊娠中・授乳中は通常、使用が制限されており、安全性に関する十分なデータがないため、医師とよく相談した上で判断する必要があります。
運動・食事とGLP-1薬の併用効果
GLP-1作動薬の効果を最大限に活かすためには、食事や運動との併用が不可欠です。薬がもたらす満腹感・食欲抑制効果をベースにしながら、栄養バランスを意識した食事(高タンパク・低糖質・高食物繊維)や、有酸素運動+筋トレを組み合わせることで、体重減少効果や代謝改善が見込まれます。
薬だけに依存するのではなく、生活習慣の見直しを含めた医療ダイエットとして取り組むことが成功の鍵となります。
用法・適応・阻害薬との関係
GLP-1薬は正しい用法・用量を守ることが極めて重要です。たとえば、マンジャロやオゼンピックでは0.25mg、0.5mg、0.75mg、2.5mg、7.5mgなど段階的に増量される設計がありますが、自己判断での増量はリスクを伴います。
また、薬の効果を妨げる可能性のある阻害薬(胃排出促進剤や代謝酵素阻害薬など)との併用には注意が必要です。薬剤同士の相互作用により、GLP-1薬の吸収・作用時間・副作用の出方が変わることがあるため、処方薬やサプリを含め、使用中のものは必ず医師に伝えてください。
GLP-1薬を安全に使うために医師と相談すべきこと
GLP-1受容体作動薬を使用する際は、以下の点を医師と事前にしっかり相談することが重要です。
- 過去の病歴(膵炎、腎機能障害、甲状腺疾患、心不全など)
- 現在の服薬内容(糖尿病薬、降圧薬、サプリメントなど)
- 体重・BMI・血糖値・HbA1cなどの検査値
- 注射or内服の選択(マンジャロ・オゼンピック・リベルサスなど)
- 用量(0.25mg〜15mg)の段階設定と増量タイミング
- 副作用が出た場合の連絡先・対応体制
定期的な血液検査・健康診断・モニタリングを行い、医師の判断のもとで安全に継続できる環境を整えることが、GLP-1薬を活用する上での基本姿勢です。
まとめ
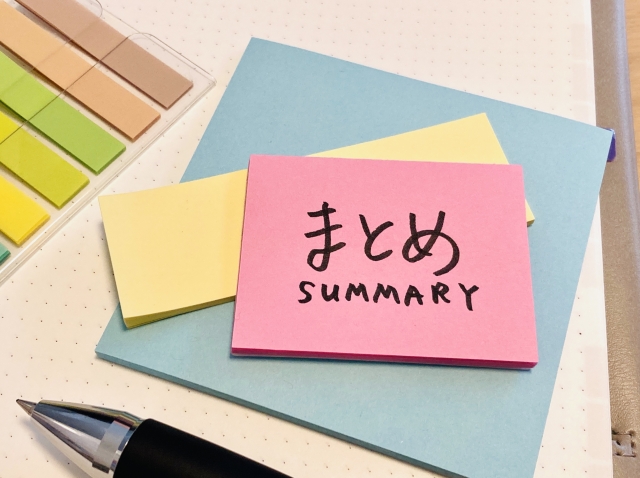
GLP-1受容体作動薬は、インクレチン作用を強化することで、血糖値のコントロールと体重抑制の両方を狙える画期的な治療薬です。2型糖尿病治療薬として認可されている製剤でありながら、その作用メカニズムから医療ダイエット分野でも注目を集めています。
製剤には、注射型・内服型があり、セマグルチド(オゼンピック/リベルサス)、リラグルチド、チルゼパチド(マンジャロ)などが代表例です。
さらに、用量設計も0.25mg〜15mg前後まで幅広く設定されており、個人の状態や目的に応じて使い分けられます。
一方で、吐き気・嘔吐・膵炎・胆石・低血糖・腎機能や心機能への影響・甲状腺への作用など、注意すべき副作用やリスクも存在します。特に自由診療での使用や高用量投与の場合は、自己判断ではなく医師の指導が必須です。
また、薬の効果を高めるには運動・食事などの生活習慣の見直しも不可欠です。薬だけに頼らず、医師との相談のもと、継続的な健康管理と検査体制を整えた上で安全に使用していくことが重要です。
GLP-1作動薬を適切に使うことで、糖尿病治療や体重管理の可能性が広がりますが、使用者自身が「正しい知識」「リスクへの理解」「習慣改善への意識」を持って取り組むことが、長期的な成功と安全性の鍵となります。
関連ページ
提携クリニック
この記事の監修
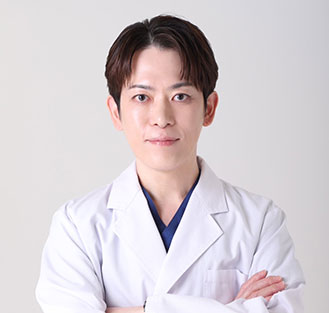
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463