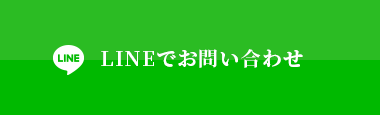GLP-1ダイエットは飲み薬でも痩せる?注射との違いや効果をわかりやすく解説

GLP-1とは?糖尿病治療から注目されるダイエット作用まで

GLP‑1(グルカゴン様ペプチド‑1)はもともと、腸から分泌され、食後に血糖値を調整するホルモンとして知られていました。これを応用した薬は、主に糖尿病の治療薬として開発されてきましたが、食欲抑制と体重減少効果も確認され、現在では、肥満治療や美容目的での応用も検討されるケースがあります。以下では、GLP‑1の基本作用と、なぜダイエットに効果をもたらすのかを、注射薬・内服薬を含めて見ていきます。
GLP-1の基本作用と体内での働き
GLP‑1は、腸から分泌されるインクレチン(消化管ホルモン)の一種です。食事をとると腸壁からGLP‑1が分泌され、膵臓に作用してインスリンの分泌を促進し、血糖を下げる働きを助けます。また、過剰なグルカゴンの分泌を抑制する働きもあり、血糖値を適切なレンジにコントロールする役割を果たしています。加えて、胃から腸への食べ物の移動速度を遅くする作用もあるため、満腹感が持続しやすくなることがあるとされています。これらの作用が組み合わさることで、食後血糖の急上昇を防ぎつつ、食事量が抑えられる傾向があるという報告もあります。
このような働きは、もともと糖尿病患者の血糖コントロールを改善する目的で設計されたものです。ところが、その中で「食欲抑制」が副次的に生じることから、近年では体重管理やダイエット用途としての応用が拡大しています。特に、GLP‑1薬には「空腹感抑制」「満腹感持続」「血糖変動抑制」の三本柱の作用があり、この組み合わせがダイエット用途で重視される要因です。
なぜGLP-1はダイエットにも効果があるのか?
GLP‑1受容体作動薬がダイエット効果をもたらすメカニズムは複合的です。食欲抑制だけでなく、血糖変動の緩和、インスリン感受性の改善、脂肪組織への影響なども関与します。具体的には、薬の作用により満腹感が出やすくなり、間食や過食を防ぎやすくなります。さらに、食後の急激な血糖上昇が抑えられることで、インスリンの過剰分泌を防ぎ、脂肪の蓄積を抑制する可能性もあります。体重が減るとインスリン感受性の改善を感じる方もおり、体脂肪の変化を報告する例もあります。
注射薬を使えば、これらの作用を強力に引き出せることが多く、比較的短期間で体重変化が出やすい傾向があります。ただし、内服薬でも、適切な吸収・血中濃度維持ができれば、注射薬に近い効果を狙うことが可能です。リベルサスのような飲み薬は、3 mgから開始し段階的に増量する方式が取られており、この増量により効果が出るラインを探りながら進める形になります。注射より穏やかに始められる点が、内服薬の利点といえます。
GLP-1の飲む薬と注射薬の違いとは?

注射薬と内服薬、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分に合った種類を選ぶためには、その違いをきちんと理解することが重要です。ここでは、飲み薬(内服薬)と注射薬の特徴、比較、そして「ダイエット目的ではどちらを選ぶべきか?」という悩みに対する視点を紹介します。
飲み薬(経口薬)の特徴とメリット
飲み薬、つまり内服薬のGLP‑1は「注射が苦手な人」に向く選択肢です。日常生活に取り込みやすく、拒否感が少ないメリットがあります。代表的な内服薬はリベルサスで、用量は3 mg、7 mg、14 mgの3種類が基本ラインです。通常は3 mgから始めて4週間後などのタイミングで7 mg、さらに14 mgへ増量することが許されています。
ただし、内服薬には吸収の制約があるため、飲み方に厳密なルールがあります。例えば、空腹時に水で飲み、一定時間は他の飲食や薬の併用を避ける必要があります。不適切な飲み方をすると、薬の吸収が悪くなり、効果が薄れてしまうリスクがあります。注射のように体内に直接届ける方式ではないため、血中濃度の安定性や最大効果の出方には制限があることを理解しておく必要があります。
注射薬の種類とその特徴
注射薬のGLP‑1には、肥満治療用に使われるサクセンダ、糖尿病治療用のビクトーザ、さらには週1回注射型のオゼンピック(セマグルチド注射)などがあります。これらは皮下注射または週1回注射などの方法で投与されます。注射薬は体内へ作用しやすい性質を持つことから、変化を実感する方があるという報告も見られます。投与スケジュールは、毎日注射するタイプ、週1回タイプなどさまざまです。
注射のデメリットとしては、注射部位の痛み、不快感、皮膚反応、注射操作の手間などが挙げられます。また、注射薬は薬剤設計上、比較的高用量を用いることが可能で、より強力な作用を狙いやすい反面、副作用のリスクも増すことがあります。
飲み薬と注射薬の「どっちがいい?」を比較
飲み薬と注射薬の間で「ダイエットにはどちらが合っているのか」と迷うケースは非常に多く見られます。注射薬は効果が出やすく、減量のスピードが速いことがありますが、注射の手間や副作用リスクの高さが懸念点です。内服薬は使いやすさや日常適用性に優れますが、効果が緩やかで最大化しにくいケースがあります。
どちらが優れているかは、個人のライフスタイル、痛みへの抵抗、注射への心理的抵抗、コスト、通院環境などに大きく左右されます。たとえば、毎日注射することが難しい人や、注射への抵抗感が強い人には、飲み薬の選択が適している可能性があります。一方で、短期間で変化を期待したい方の中には、注射薬を選ぶケースもあります。最終的には、医師との相談を通じて、自分に合う方を選ぶことが望ましいです。
リベルサスとは?日本で承認されたGLP-1飲み薬の特徴

飲み薬タイプのGLP‑1で日本で正式に承認されているのがリベルサスです。このセクションでは、リベルサスの性質、服用方法、副作用、さらに注射薬との比較ポイントまで詳しく見ていきます。
リベルサスの概要と有効成分
リベルサスは、セマグルチドを有効成分とする経口GLP‑1受容体作動薬で、日本国内でも承認されている数少ない内服薬です。注射薬と同じセマグルチドを使用していますが、体内への吸収方式が異なるため、効果の出方や安全性プロファイルに違いがあります。リベルサスの用量は3 mg、7 mg、14 mgの3種類があり、通常は3 mgからスタートし、段階的に増量していきます。最初は耐性や副作用を抑えるために低用量から始めることが一般的です。
使用方法と服用時の注意点
リベルサスを服用する際は、非常に厳しい飲み方ルールを守る必要があります。まず、起床後、まだ飲食をしていない状態で、水(コップ半分程度)で3 mg錠または指定された用量を飲むことが基本です。その後少なくとも30分は他の飲食や他の内服薬の併用を避けなければなりません。これを破ると、薬の吸収が阻害されてしまい、期待される効果が出にくくなります。服用中は、胃腸の調子や体調変化を観察する必要があり、異常を感じたらすぐに医師に相談することが大切です。また、増量は段階的に行われ、通常4週間以上経過後に7 mg、さらに14 mgまで上げるケースが一般的です。なお、増量ペースは個人差があり、体調や副作用を見ながら慎重に決められます。
リベルサスと注射薬の比較ポイント
リベルサスには「飲み薬」という利便性がある一方、注射薬と比べて作用がマイルドであることが多い点が特徴です。注射薬は用量や薬設計の自由度が高く、より強い食欲抑制や減量効果を実現しやすい設計です。さらに、注射薬は血中への到達が速く、安定性の面でも有利な点があります。ただし、注射薬は注射操作、注射部位への負担や痛み、通院の手間などのデメリットも伴います。
また、内服薬は保険適用の有無が注目される点です。リベルサスは2型糖尿病治療薬として承認されており、糖尿病患者に対しては保険適用の対象となります。しかし、ダイエット目的での使用は、ほとんどの場合保険適用外となり、処方を受ける際は自由診療になるケースが多いです。注射薬も同様に、肥満治療目的では保険適用外となることがほとんどです。こうした保険適用の違いも、注射薬と内服薬を比較する上で無視できない要素です。
ダイエット目的でのGLP-1使用|医療機関での選択肢と注意点

GLP‑1をダイエット目的で使う場合、医療的な適応や制限、処方の流れ、個人輸入や薬局での扱いなどにも目を向けなければなりません。この章では、それらの視点と、医師と相談すべきポイントを解説します。
「痩せる薬」ではないGLP-1の正しい理解
GLP‑1薬は魔法の「痩せ薬」ではありません。あくまで体の仕組みを利用して減量を助ける補助的手段です。薬を継続することで体重に変化を感じる方もいますが、使用を中止した際に変化が元に戻るように感じられる方もあるようです。単に薬に頼るだけでなく、食事内容の見直し、運動、睡眠改善といった生活習慣の変化を並行して行うことが、効果を維持し成功につながる道です。
医療ダイエットとしての適応と制限
GLP‑1薬を処方できるかどうかは、医療機関の方針や法的・倫理的な枠組みによります。肥満であり、他のダイエット法で改善しなかった、BMI基準を満たしているなどの条件を設けている施設もあります。ダイエット目的で使うケースでは、保険適用が認められないため、自由診療となることが一般的です。薬局で市販されているわけではなく、必ず医師の処方を受けなければ手に入りません。また、個人輸入による入手も不正確な製品を使うリスクがあるため、慎重さが求められます。
医師と相談すべきポイントとは?
GLP‑1薬を試す際には、医師に対し現在の体重、基礎疾患、服用中の薬、過去の副作用歴、腎機能・肝機能などを正確に伝える必要があります。糖尿病を既往している場合は、併用薬との相互作用や低血糖リスクの調整も重要です。また、薬開始後は定期的な診察で経過をチェックし、効果や副作用をモニタリングすることが必須です。効果が乏しいと判断されれば用量を変更したり、注射薬への切り替えも検討できます。さらに、やめるタイミング、リバウンド防止策も含めてあらかじめ医師と計画を立てることが成功のカギです。
副作用とリスク|GLP-1製剤を安全に使うために
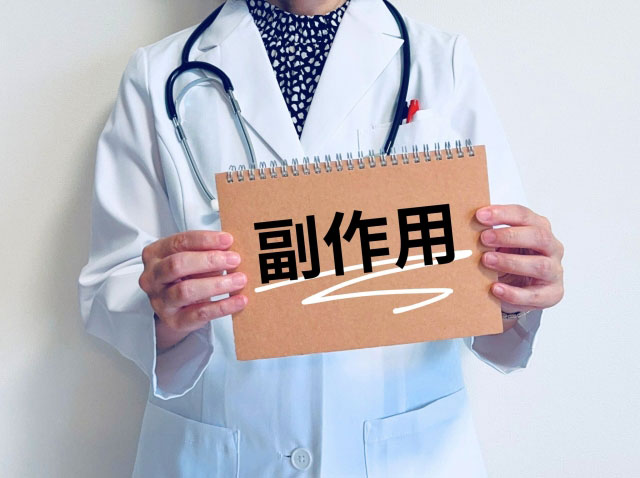
GLP‑1薬は効果が魅力的ですが、副作用・リスクへの配慮なしには利用できません。この章では、よく見られる副作用とその対処法、注意すべき禁忌事項、そして総まとめとして、安全に使うための視点を述べます。
よくある副作用(吐き気・下痢など)と対処法
GLP‑1薬を服用または注射する際、もっとも頻度が高い副作用は胃腸症状です。吐き気、むかつき、胃の不快感、下痢や便秘などが典型的です。特に使用初期の2週間程度が体調変化のピークとされ、この期間は注意深く経過を観察する必要があります。多くの場合、体が薬に慣れるに従って症状は和らぎます。副作用が強い場合は、用量を調整したり、食事を少なめ・消化に優しい食品に変えることで緩和を図ります。一方で、膵炎や胆嚢疾患といった重篤な副作用が生じるリスクもゼロではありません。こうした症状(激しい腹痛、持続的な嘔吐、血便など)に気づいたら、直ちに服用を中止し、医師に相談する必要があります。
注意が必要なケースと禁忌事項
GLP‑1薬には使ってはいけないケースがあります。1型糖尿病や糖尿病性ケトアシドーシス、重度の消化管障害などは明確な禁忌です。また、腎機能や肝機能が悪い人、妊娠中・授乳中の人、薬のアレルギー歴がある人なども慎重に扱う必要があります。こうした条件がないかどうかは、事前の問診・検査で医師が判断すべきです。無自覚に使うと健康に重大な影響を及ぼす可能性がありますので、自己判断で始めることは避けなければなりません。
まとめ

GLP‑1製剤は、糖尿病治療薬として開発された医薬品でありながら、その副次的な作用として「体重減少効果」が注目され、現在ではダイエット目的でも医療現場で活用されるようになっています。注射薬と飲み薬(内服薬)という2つの主要な形が存在し、それぞれに異なる特徴があります。
注射薬は血中到達性が高い設計のため、変化を感じやすい場合もあるとされています。特にサクセンダやビクトーザなどは、糖尿病患者だけでなく、肥満に悩む人々にも支持されてきました。毎日注射するタイプや週1回で済むタイプなど種類も増え、ライフスタイルに合わせて柔軟な選択が可能になっています。
一方、リベルサスに代表される内服薬は、「注射に抵抗がある」「毎日の自己注射が負担になる」といった人々にとって、有力な選択肢となっています。3mgからスタートし、体に慣らしながら7mg、14mgへと段階的に増量していくことで、副作用を抑えつつ効果を高めていく工夫がされています。正しい飲み方を守ることで、注射薬に劣らない効果を引き出すことも期待できます。
とはいえ、GLP‑1製剤はあくまで“痩せる薬”ではなく、医師の指導のもと、生活習慣改善を前提に使うべき「補助的な医療ツール」です。どれほど優れた薬でも、暴飲暴食や運動不足といった根本原因を改善しなければ、リバウンドや副作用のリスクが高まります。また、GLP‑1薬はやめたら体重が戻る可能性もあり、「その後」の過ごし方が結果を左右します。
選択に迷ったときには、「注射薬と飲み薬のどちらが自分に合っているか」という視点だけに偏らず、効果の出方、副作用のリスク、自分のライフスタイル、続けやすさ、そして医師の判断を総合的に考慮して決めることが大切です。
薬に頼るだけでなく、「どうやって痩せるか」だけでなく「痩せたあとどう過ごすか」にも意識を向け、GLP‑1を健康的な減量のための“選択肢の一つ”として、賢く安全に活用していきましょう。
関連ページ
提携クリニック
この記事の監修
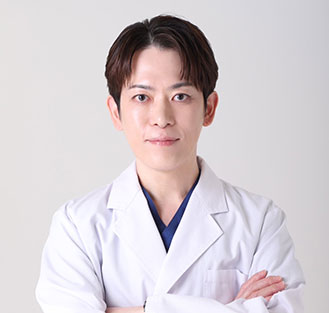
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463