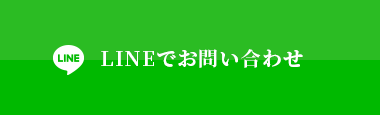GLP-1ダイエットとは?糖尿病治療薬を使った最新痩身法とクリニックの選び方を徹底解説

GLP-1ダイエットとは?— 痩せる仕組みと注目される理由
「GLP‑1ダイエットとは」、糖尿病治療薬として開発されたGLP‑1受容体作動薬を用いた医療機関での肥満治療に使用されることのある方法のことを指します。注射や内服薬を用いて、食欲を抑制しつつ血糖値のコントロールを目指す仕組みであり、最近ではオンライン診療やクリニックでの対面外来でも処方されるケースが増えています。では、その働きや注目される理由を見ていきましょう。
GLP-1受容体作動薬とは
GLP‑1受容体作動薬とは、インスリンの分泌を促進し、血糖値を安定させながら食欲を抑える作用を持つ「作動薬」です。本来は2型糖尿病治療薬として承認された薬ですが、肥満に対して一定の有用性を示す研究もあります。ただし、肥満治療としては未承認です。食後の血糖値の急上昇を抑え、満腹感を長く持続させるメカニズムによって、空腹感の頻度を減らし、食べ過ぎを抑える可能性があるとされています。
セマグルチドやリラグルチドなどのGLP‑1作動薬には、注射タイプと飲み薬タイプがあります。特に「注射マンジャロ」や「サクセンダ」などの薬は、海外や日本でも使われ始めており、効果と副作用のバランスを医師が見極めながら処方を行います。
肥満や糖尿病との関係
このダイエット法が「痩せる仕組み」として注目されるのは、肥満と2型糖尿病が深く関連しているためです。肥満になってBMIが高めになったり、40代・50代で代謝が落ちてきたりすると、内臓脂肪が増えてインスリンの作用が低下し、血糖値が上昇しやすくなります。そうすると、2型糖尿病を発症するリスクが高まり、さらに体重が減りにくい体質になってしまうという悪循環が生まれます。GLP‑1作動薬はその循環を断つ可能性を含んでおり、満腹感を増すことで「お腹 すく」状態を減らし、食事量をコントロールしやすくします。そして血糖値の上昇を抑えることで、糖尿病の治療と同時に体重管理への応用が検討されることもありますが、医師の判断が重要です。ただし、肥満だからといって必ず使用できるわけではなく、健康診断の結果、BMI、血液検査、生活習慣、医師の診断のうえで「適応」があるかどうかが決まります。
医療機関での処方とその背景
GLP-1ダイエットは医療機関を通して行われるものです。クリニック(対面)での診察は当然ですが、近年はオンラインクリニックというネットを活用した診療形態も増えています。オンライン診療で医師の問診・血液検査手配・薬の処方を行うことが可能になり、自宅からでもスタートができる環境が整ってきています。しかし、適切な医療ダイエットとしての使用には医師会や厚生労働省が「適応外使用」や「個人輸入」の危険性について注意を促しています。薬の適応や用量、安全性が明確でないまま使用すると、リスクを伴うためです。こうした背景を理解した上で、クリニックやオンライン診療を通じた治療を選択することが重要です。
GLP-1薬の種類と違い:注射・飲み薬どっちがいい?

ここからは、「GLP‑1薬」と呼ばれる医薬品の具体的な種類や形式を、注射タイプと飲み薬タイプに分けて比較し、「どっちが自分に合っているか」を考えてみましょう。
オゼンピックの特徴と毎週注射の仕組み
「オゼンピック」(一般名:セマグルチド)は、週に1回の皮下注射タイプのGLP‑1受容体作動薬です。皮下に注射を行う形式ですが、毎日飲む必要がないため、忙しい40代・50代の方や注射に抵抗がない方に選ばれています。この注射タイプでは、体内に長く作用するため、満腹感の持続が期待され、食事の調整に役立つことがあります。また血糖値の安定化にも寄与するため、2型糖尿病の治療と痩身の目的が重なる場合に注目されます。ただし、注射の手間、自己注射の手技、費用、副作用など(例えば吐き気、便秘、低血糖のリスク)などをよく理解する必要があります。特に自分で注射を打つ場合は、クリニックのフォローがあるか、注射量がどのように調整されるかを確認してください。
リベルサスの特徴と毎日の飲み薬の特徴
「リベルサス」は、GLP‑1受容体作動薬の中でも経口、つまり毎日の飲み薬タイプとして提供されている製剤です。注射に抵抗がある方や、毎日薬を飲む習慣がある方には選ばれることが多いです。飲み薬タイプでは、食事前後の手間が少なく、ネットでのオンライン診療と連動しやすいメリットがあります。ただし、毎日薬を飲む継続性が求められ、注射タイプに比べて血中濃度の維持や「満腹感を持続させる力」の面で違いがある可能性があります。副作用として、吐き気や便秘、下痢などの消化器症状が報告されており、使用中は健康診断や血液検査でモニタリングを行うことが推奨されます。また、薬だけに頼ると痩せにくくなったり、リバウンドにつながるため、食事・運動との併用が重要です。
注射と飲み薬の違いと選ばれる理由とは?
注射タイプと飲み薬タイプ、どちらがいいかは個人のライフスタイルや体質、そしてクリニックでの医師の判断によります。注射タイプは週1回などのペースで済むため、毎日の薬を忘れやすい方には向いています。一方で、飲み薬タイプは毎日服用が必要ですが、注射が苦手な方や通院回数を減らしたい方にはメリットがあります。比較してみると、注射は満腹感の維持が期待され、飲み薬は習慣化しやすい点が特徴です。どちらにせよ、薬(GLP‑1作動薬)は「糖尿病治療薬」であるという本来の働きを理解し、クリニック・医師会・厚生労働省のガイドラインを踏まえて使うことが、安全性と効果を保つために重要です。
体重が減りにくい場合に考えられる要因

GLP‑1ダイエットを始めたものの「40代」「50代」で思うように体重が落ちない、お腹まわりが変わらないといった悩みを持つ方へ、体重が減りにくい原因を掘り下げていきます。
食事・運動との併用の重要性
薬だけでは飛躍的に体重が落ちるわけではありません。GLP‑1受容体作動薬によって満腹感が高まったり食欲が落ちたりしても、食事の内容や運動習慣がそのままでは「痩せない」という問題が残ります。特に、筋肉量が低下してしまうと基礎代謝が落ち、BMIが高めの40代・50代では運動習慣がないとリバウンドのリスクが高くなります。食事においては、摂取カロリーを減らしながらも良質なタンパク質を確保し、満腹感を得やすい野菜を先に食べるなどの工夫が有効です。運動では、有酸素運動とともに筋トレを取り入れ、筋肉を維持することで健康診断の結果にも好影響を与えます。GLP‑1薬の作用を補助する目的で、クリニックでの血液検査や健康診断を活用し、医師のアドバイスを受けながら生活習慣を整えていくことが目的となります。
経過観察期間の考え方(週単位での見方)
体重の経過は「週」単位でゆっくり確認することが大切です。注射タイプであれば毎週の投与が定められていることが多く、最初の4~8週は体が薬に慣れる期間とされます。急激な減量を目的にすると、「痩せない」と感じてモチベーションが下がることがあります。本来の目的は健康を改善しつつ「痩せた状態」を維持することであり、クリニックで医師と共有する血糖値、体重、BMI、満腹感、食欲の変化を記録することで進捗を確認できます。週ごとのチェックを通じて、どのくらい食事や運動を改善していけばよいか、薬の量をどう調整するかなどを医師と相談できる環境を整えましょう。
医薬品のみに依存することによる限界
GLP‑1作動薬は強い補助となる可能性がありますが、薬だけに依存すると「その後」のリバウンドや痩せない状態になるケースもあります。実際、薬を中止したときに体重が戻ることや、食事量を戻したらBMIが再上昇したという報告もあります。特に、筋肉量が落ちて基礎代謝が低下したままだと、痩せにくい体質が残ってしまいます。薬は補助的な手段であり、真の目的は食事・運動・生活習慣を変えること、健康診断で良好な数値を保つことです。クリニックにおいて、注射の量・頻度・飲み薬との比較などを医師とともに検討しながら進めることが重要です。
使用上の問題点とリスクへの理解

GLP‑1ダイエットとは言え、薬を使用する以上は安全性や副作用、リスクをしっかり理解する必要があります。ここでは、注意すべきポイントを解説します。
胃腸症状・低血糖・アレルギー反応など
GLP‑1受容体作動薬を使用する際に見られる代表的な副作用には、吐き気、便秘、下痢、腹痛などの胃腸症状が含まれます。また、糖尿病治療薬としての性質を持つため、低血糖(血糖値が過度に低くなる状態)というリスクもあります。低血糖になると、お腹がすく感覚が強くなったり、冷や汗、顔面蒼白、動悸などの症状が現れることがあります。加えて、アレルギー反応や急性膵炎、腸閉塞といった重篤なリスクがあるため、医師が健康診断や血液検査で状態を確認しながら処方量や頻度を決める必要があります。クリニックでのフォロー体制が整っていること、オンライン診療であっても緊急時の連携があるかどうかを確認しましょう。
長期間の使用に対する現時点での見解
長期的にGLP‑1作動薬を使用することについては、現時点での論文やデータはまだ限定的です。海外、特にアメリカでは肥満症を適応としたGLP‑1受容体作動薬が承認されており、注射タイプ・飲み薬タイプともに体重減少効果が報告されています。しかし日本国内では、2型糖尿病の治療薬として承認されているだけであり、ダイエットとは直接の目的として承認されていないため、厚生労働省や日本糖尿病学会から「適応外使用」の注意喚起が出ています。また、使用中止後の体重維持やリバウンドの観点からも、医師監督のもと、健康診断・血液検査・運動・食事を含めた総合プランが必要です。個人輸入やネット購入による自己判断での使用は危険性を伴います。
使用中止や変更が必要となるケースとは
使用中に「効果が出ない」「思ったほど痩せない」「副作用(吐き気やお腹がすく・便秘など)が強い」「低血糖が頻発する」「筋肉量が極端に落ちて代謝が下がった」などの状況が発生した場合には、医師が薬の量・頻度・種類の変更や中止を検討します。また、適応外使用やクリニック/オンライン診療ではフォローが不十分な場合、危険性が高まるため、専門クリニックでの対面診療を検討すべきです。治療目的、費用、注射か飲み薬か、通院頻度、健康診断・血液検査の実施体制などを事前に確認しておくことが適切です。
自分に合った治療環境を選ぶ:オンライン or 対面クリニック

医療ダイエットの一つである「GLP-1ダイエット」を始める際には、治療を受けるクリニックの環境にも注目しましょう。オンライン診療と対面クリニック、それぞれの特徴や選び方のポイント、違いについてご紹介します。
オンラインクリニックの特徴とメリット・デメリット
オンラインクリニック、つまりネット診療・オンライン診療を用いた治療では、スマートフォンやパソコンを通じて医師の診察や処方が受けられ、注射や飲み薬の相談をリモートで済ませることができます。通院の手間が省け、時間的余裕が少ない40代・50代の方にも向いています。しかし、注射が必要なケースでは自己注射となる可能性があり、医師や看護師が直接体を診るわけではないため、安全性やリスク(副作用・低血糖)への対応力には限界があります。健康診断や血液検査がちゃんと行えるか、リバウンド対策や筋肉維持・運動支援のフォローがあるかといった確認が必要です。個人輸入を介した自己判断での使用やネットだけの処方は、厚生労働省が注意を促しているように危険性があります。
対面クリニックの安心感と対応力
対面クリニックでは、医師が直接患者の体調を確認し、血液検査や健康診断、体重・BMI・体脂肪・筋肉量の測定などをその場で行えます。注射タイプのGLP‑1作動薬では、初回にクリニックで使用方法(注射器の使い方・量の調整)を受けることで安心してスタートできます。また、副作用が出た場合の迅速な対応が可能で、筋肉量維持やリバウンド防止のための運動・食事アドバイスもきめ細やかです。費用はオンラインに比べやや高めになることがありますが、安全性やフォロー体制を重視する場合にはおすすめです。
保険適用と自由診療の違い、費用感の目安
「GLP‑1薬」は日本国内では、2型糖尿病の治療薬として承認されており、肥満症の場合でも一定の条件を満たせば保険適用となるケースがあります。ただし「ダイエットとは純粋に痩せる目的」というだけでは保険適用は難しく、自由診療扱いとなることが多いです。自由診療では、薬代・注射代・クリニック費用をすべて自己負担するため、月に2万円〜4万円程度かかるケースもあります。注射か飲み薬か、通院頻度やサポート内容、血液検査・健康診断をどれだけ実施するか、オンラインか対面かという環境によって費用に差が出ます。クリニックを選ぶ際には、適応(BMI・体脂肪・糖尿病・インスリン・血糖値)や医師の診察体制、注射の手技、服用量、安全性、副作用への対応、リバウンド対策といった総合的な観点で確認しましょう。
GLP-1薬の使用は誰に向いている?向いていない?

ここでは、「GLP-1ダイエット」がどのような方に向いているのか、また反対に向いていないのはどんな方なのかを整理します。医師が判断する際のポイントや、薬本来の目的、使用前に知っておくべき注意点についても解説します。
医師が考慮する健康状態と生活習慣の要素
医師がGLP‑1受容体作動薬を処方する際に見る主な要素には、健康診断の結果、血液検査による血糖値・インスリン抵抗性・脂質異常・高血圧などの有無、BMIの数値、体脂肪量、筋肉量、年齢(特に40代・50代)、生活習慣(食事・運動・喫煙・飲酒)などがあります。また、2型糖尿病を既に発症していたり、肥満症で食事・運動だけでは改善が難しかったりするケースが対象となることが多いです。反対に、健康な成人が単に「体重を減らしたい」「20キロ痩せたい」という目的だけで薬を使うのは、医師会や厚生労働省の観点から慎重になる必要があります。
糖尿病治療薬としての本来の役割について
もともとGLP‑1受容体作動薬は、2型糖尿病の治療を目的として開発・承認された薬です。インスリン分泌を促し、食後の血糖値の上昇を抑え、血糖コントロールを支援する働きがあります。日本国内ではこの適応で承認されており、ダイエットとは別の目的で使用される場合には「適応外使用」とされ、安全性・有効性が十分に確認されていないため、医師の判断と慎重な管理が求められます。つまり薬の主な「働き」は糖尿病の治療であり、痩身を目的とした使用には制限があるという認識が大切です。
医療ダイエットとしての使用は適応外である点の留意
日本においては、ダイエット目的でのGLP‑1作動薬の使用は、現時点では「痩せる目的(ダイエットとは)」としての承認がない、あるいは限られた適応しかないケースがほとんどです。厚生労働省や製薬企業、医師会がインターネット上の「ネット通販」「個人輸入」「美容・痩身目的」の薬の使用に対して注意を呼びかけています。個人輸入やネットだけでの購入、クリニックのサポートが不十分な場所での使用は危険性を伴い得ます。医療ダイエットとして取り組む場合には、信頼できるクリニック(対面/オンライン)で医師の診断を受け、食事・運動・生活習慣を含めた包括的なプログラムを活用することが望まれます。
効果を補助する生活習慣:食事と運動の工夫

薬を使うだけでは「ダイエットとは」呼べません。ここでは、GLP‑1ダイエットを成功させるために不可欠な生活習慣として、食事と運動の具体的な工夫を見ていきます。
摂取カロリーと満腹感のバランスを意識した食事法
GLP‑1受容体作動薬は、満腹感を感じやすくし、食事の量を自然に減らせる可能性があります。しかし、食べ物の質や摂取カロリーを考えずに薬だけに頼ると「痩せない」「リバウンド」という問題に直面します。まず、食事の前に野菜を食べる、咀嚼回数を増やして満腹感を高める、良質なたんぱく質を摂る、極端な糖質制限ではなくバランスを意識することが大切です。また、食事の回数や時間帯に配慮し、夜遅くに大量に食べると血糖値が上がりやすく、薬の効果が十分に活かせない可能性があります。特に、「お腹 すく」状態を頻繁に作らないよう、間食の質や量を見直し、筋肉を維持するための栄養も忘れないでください。
運動習慣と代謝維持の関係
運動は、体重減少だけでなく、筋肉量を維持し代謝を高めることで「痩せてその後もキープ」するために重要です。特に40代・50代では、代謝が落ち筋肉量が減りやすいため、薬を使って満腹感を高めて食事量を減らすだけでは限界があります。有酸素運動(ウォーキング・ジョギング)とともに、軽めの筋トレやストレッチを取り入れることで、筋肉を維持し、リバウンドしにくい体質を作ることができます。こうした運動習慣とともに血糖値・BMI・体脂肪率のチェックをクリニックで行うことで、健康診断結果の改善や効果の確認が可能です。
継続的な体重管理とリバウンド予防の視点
ダイエットの目的は「痩せる」だけでなく「痩せた状態を維持する」ことです。薬を止めた後、または使用量を変更した後に、体重が戻る=リバウンドが起きる人もいます。そのため、減量期から維持期への移行を考えて、体重・筋肉量・BMI・血糖値を定期的にチェックし、食事・運動の習慣を見直し続けることが必要です。クリニックやオンライン診療を通じて、医師や専門スタッフと「その後」の管理プランを立てることが成功の鍵です。薬だけに頼らず、生活習慣改善を目的として食事・運動と薬を組み合わせることが、GLP‑1ダイエットとは言える本質です。
まとめ
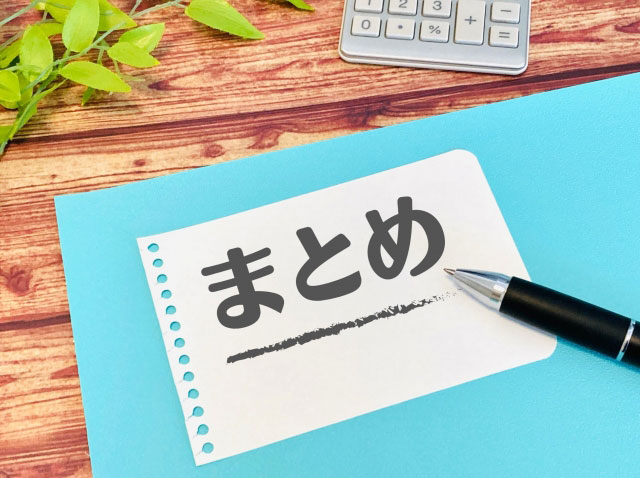
これまで、GLP‑1ダイエットとは何か、薬の種類(注射・飲み薬)、体重が減りにくい場合の要因、使用上のリスク、自分に合った治療環境、そして生活習慣の補助方法までを一貫して解説しました。GLP‑1作動薬は、糖尿病の治療薬としての本来の役割があり、医師会・厚生労働省が適応外使用に関して注意を促している中で、「痩せる目的」のみでの使用には慎重になる必要があります。オンライン診療もクリニック選びの選択肢として広がっていますが、安全性・費用・フォロー体制という面では、対面クリニックを選ぶことも強くおすすめです。薬を使う際には、必ず医師の診察を受け、血液検査・健康診断・BMI・体脂肪・筋肉量・血糖値のチェックを行った上で、自分に合った治療方法を選びましょう。食事・運動・薬という三本柱をバランスよく使って、リバウンドせずに「痩せた」「健康になった」状態を維持していくことが、GLP‑1ダイエットとは真に意味のある医療的ダイエットと言えます。
関連ページ
提携クリニック
この記事の監修
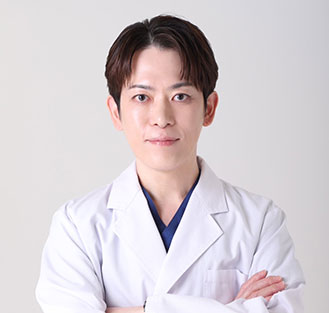
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463