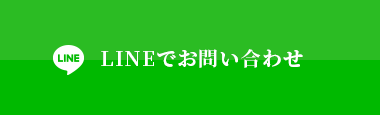くいしばり・歯ぎしりを軽減!ボトックス注射による噛み締め改善法

ボツリヌストキシン注射のメカニズムとは
「噛む力を抑える」という意外なアプローチとして、ボトックス注射(ボツリヌストキシン注射)が近年注目されています。
無意識に歯を強く噛みしめたり、寝ている間に歯ぎしりをしていると、顎まわりの筋肉(特に咬筋や側頭筋)が過度に緊張し、歯・顎・首・肩などに負担をかけることがあります。
ボトックス注射では、その筋肉に直接注射することで、神経から筋肉への興奮伝達を一時的にブロックし、筋肉の収縮を和らげます。
結果として「強く噛む癖」「食いしばり」「歯ぎしり」による負荷を軽減する効果が期待されます。
また、筋肉の張りがやわらぐことで、顔の輪郭がすっきりする「小顔効果」が副次的に得られるケースもあります。
食いしばり・歯ぎしりに対する効果の理由
食いしばりや歯ぎしりでは、無意識のうちに顎を強く締め付けることで、歯が摩耗したり、詰め物が外れやすくなったり、顎関節・首・肩にまで影響が及ぶことがあります。
ボトックス注射により筋肉の強い収縮を抑えることで、歯や顎への過剰な力が軽減され、結果として症状改善につながると考えられています。
マウスピース治療との違いと併用可能性
従来の対策としてよく使われるのが、ナイトガードと呼ばれるマウスピースです。これは睡眠中に歯の直接接触を防ぐ装置で、歯そのものへのダメージを抑える点で効果的です。
一方でボトックス注射は、「噛む力そのもの」を筋肉レベルで軽減するアプローチであり、マウスピースとは異なる視点からの対策といえます。多くのクリニックでは必要に応じて併用が行われ、より総合的に症状を緩和していきます。
クリニックで受けられるボトックス治療の流れ

ボトックス治療は美容外科や自由診療クリニックで広く行われており、食いしばりや歯ぎしりの対策としても注目を集めています。
注射の部位(咬筋)と施術の所要時間
噛みしめの原因となる主な筋肉は「咬筋(こうきん)」と呼ばれ、フェイスラインのエラ部分に位置します。必要に応じて、側頭部にある「側頭筋(そくとうきん)」へも注入が行われることがあります。
施術は、基本的に麻酔を使用せずに行われ、所要時間は10〜20分程度。
美容目的の小顔ボトックスよりも、少量で行うケースが多いため、ダウンタイムも少なく、初めての方でも比較的受けやすい施術です。
治療の流れと施術後の注意点
カウンセリングでは、噛みしめの癖や症状の程度を確認しながら、最適な注入部位や単位数を提案してもらいます。咬筋の発達具合や、日常生活でのストレス・習慣などもヒアリングの対象になります。
施術後は、強く噛みしめる動作や硬い食事を2〜3日程度控えることが推奨される場合があります。また、より効果を長持ちさせるために、首・肩まわりを温めたり、リラックスを意識した生活習慣の見直しが効果的です。
痛みや腫れなど、施術直後の反応について
ボトックス注射は極細の針を使用して行うため、痛みは最小限です。ただし、施術直後に赤みや軽度の腫れ、内出血が出る場合があります。ほとんどは数時間〜数日で自然におさまります。
まれに、筋肉の反応によって一時的に違和感を覚えるケースもありますが、過剰に不安になる必要はありません。気になる場合は施術クリニックに早めに相談すると安心です。
効果はいつから?どれくらい続く?

注射治療を受ける前に「効果はいつ出るのか」「どれくらい持つのか」「再施術はいつか」を把握しておくと安心です。ここではそのポイントを解説します。
注射後に現れる効果のタイミング
ボトックス注射の効果は、注射後数日〜2週間以内に現れはじめます。早い人では1週間程度で「食いしばりが楽になった」「顎のだるさが減った」と感じることもあります。
効果の持続期間と再施術の目安
効果の持続期間はおおよそ3〜4ヶ月が目安です。時間の経過とともに筋肉の動きが徐々に戻ってくるため、再注射のタイミングは4〜6ヶ月に一度が一般的とされています。
継続的に受ける場合のリスクと注意点
継続的に治療を行うことで、筋肉が注射に慣れてしまい効果が薄れる「抗体産生」などのリスクがあるとされます。
また、必要以上に注射すると噛む力が落ちすぎて、表情が硬く見えたり、食事のしにくさを感じることもあります。必ず医師と相談し、適切な頻度・量で施術を行うことが大切です。
ボトックス治療のメリット・デメリット

治療を受けるにあたって、メリットだけでなくデメリット・リスクも正しく理解することが重要です。ここではその両面を整理します。
歯への負担軽減・エラ張りの緩和などのメリット
ボトックス注射によって咬筋の過剰収縮が抑えられると、歯の摩耗・歯根破折・顎関節の痛みの軽減が報告される場合があります。ただし、適応・効果には個人差があり、施術担当医と相談のうえ検討されることが重要です。また、エラ張りが気になる方には、咬筋肥大の改善により小顔・こめかみ・口角周辺のシャープ化という美容的な副効果も得られやすく、30代・40代の方に選択されることもありますが、年齢・症状・筋肉量・生活習慣などによって適応は異なります。肩・肩こり・首の張りが併発しているケースでは、肩ボトックスと併用してよりスッキリとした印象に整えることも可能です。
表情の違和感や噛みにくさなどのデメリット
一方で、治療の量や単位・注入部位が適切でないと、表情が硬く見えたり、口角が下がったり、噛む力が弱くなって噛みにくさを感じたりすることがあります。さらに、首・肩・顎のバランスが崩れたまま注射してしまうと「肩こりの方も同時に治療すべきだった」と後悔するケースがあります。
副作用や過度な効果によるリスクも理解しよう
注射後には痛み・腫れ・内出血・赤みなどが一時的に出ることがあります。まれに注射部位の筋肉が弱くなりすぎて、噛む・喋る・食べる動きに影響を及ぼす可能性もあります。量が適切でなかった場合や専門医師ではない施術時に、肩・こめかみ・側頭筋など他筋肉への影響が出ると「リスクが高かった」「失敗だった」という声もあります。こうした点を踏まえ、歯医者または美容外科での注射治療では、明確に「治療」「予防」「噛みしめ抑制」の目的を確認した上で進めることが重要です。
ボトックス治療の費用と保険適用の可否
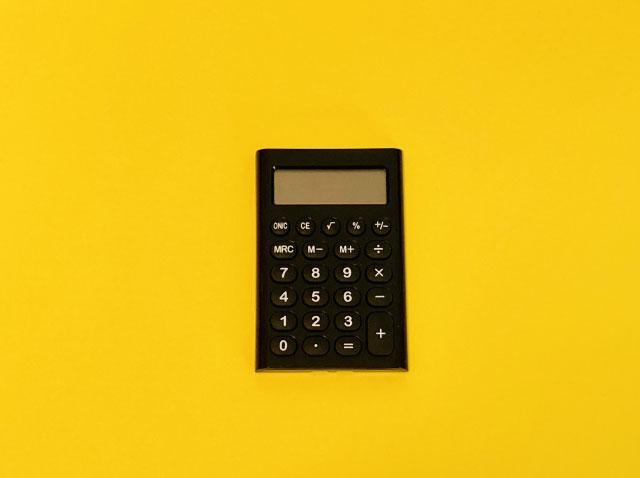
治療を受ける上では、費用や保険適用の可否、施術を行うクリニック選びが重要になります。
自由診療が基本、費用相場は数万円〜
ボトックスによる食いしばり・歯ぎしり治療は、基本的に自由診療です。
費用は施術部位や注入量によって異なりますが、咬筋のみであれば1回あたり3〜10万円程度が相場です。
保険適用される条件と「治療」としての位置づけ
ボトックスによる歯ぎしり・食いしばりの対策は、多くの美容クリニックでは自由診療として提供されています。
しかし、症状が重度で日常生活に支障が出ている場合(たとえば、強い顎の痛みや慢性的な頭痛、歯の破損など)は、医療機関での処置が必要と判断され、保険診療の対象になるケースもあります。
ただし、美容目的(小顔・フェイスライン調整)とみなされた場合は保険適用外となるのが一般的です。
そのため、施術を受ける際には、「この治療は医療目的なのか、美容目的なのか」を明確にし、保険適用の対象となるかどうかを事前にクリニックで確認することが重要です。
ボトックス注射以外の治療法との比較
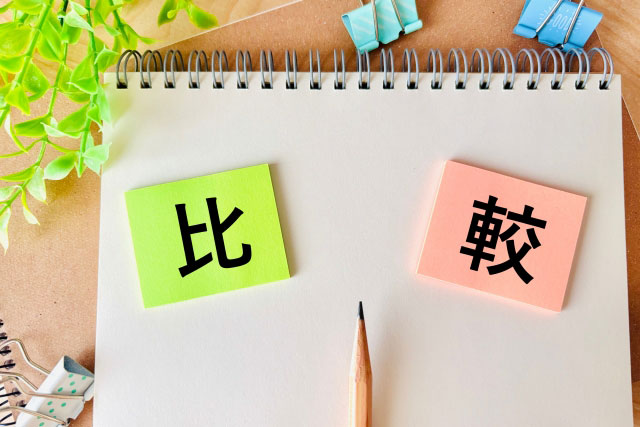
ボトックスだけではなく、歯ぎしりや食いしばりに対する他の治療法も理解しておくと選択肢が広がります。ここでは代表的なものを比較します。
マウスピース治療のメリット・限界
マウスピース治療は、歯や顎関節への直接的なダメージを抑えるための第一選択となることが多く、顎や歯の摩耗・歯根破折・エナメル損耗などを防ぐ点で有効です。しかし、マウスピース単独では顎周りの筋肉の過剰収縮自体を抑えることが難しく、特に肩・顎・背中の筋肉連動があるケースや睡眠中の無意識噛みしめには限界があります。
顎関節症治療との関連性と併用可能性
顎関節症(TMJ/TMD)を伴う歯ぎしりに対しては、マウスピースの使用や理学療法、ストレス管理、姿勢改善などが一般的な対応とされています。
一方で、美容クリニックで行われるボトックス注射によって、咬筋や側頭筋の緊張を緩和することで、こうした治療と併用しながら症状の改善を図るケースも増えています。
特に、肩こり・食いしばり・側頭部の筋肉の張り・首・背中の筋肉との関連が強い場合には、全身の筋肉バランスを意識した総合的なアプローチを美容クリニックで相談することが、後悔のない治療選択につながります。
相談時に確認すべきポイント
治療を始める前には、以下のような内容を確認しましょう。
- 食いしばりの原因と筋肉の状態
- 注射する部位とその理由
- 注射量・単位・費用
- 効果の持続期間と再施術の時期
- 副作用やリスクの説明があるか
- 小顔目的か治療目的かの明確化
こんな方におすすめの治療法とは?ライフスタイル別に見る選び方

ボトックス治療は誰にでも適しているわけではありません。ここでは、どんな悩みを抱える人に向いているのか、逆に注意が必要なケースを解説していきましょう。
歯ぎしりによる症状が日常生活に影響している人へ
「朝起きると顎がだるい」「歯の一部が欠けた」「睡眠中に音を立てていると家族に言われる」など、明確に歯ぎしり・食いしばりの症状が現れている方にとって、ボトックス注射は有力な治療法になり得ます。
また、マウスピースを装着しても改善されない、あるいは継続が難しいという方にも適しています。
特に、仕事中に無意識に噛み締める習慣がある人や、ストレスの多い生活を送っている方には、筋肉の緊張を緩和する意味でもおすすめです。
ただし、妊娠中や授乳中の方、アレルギー体質の方などは、施術前に必ずクリニックの医師に相談するようにしてください。
治療後の経過を記録する習慣も大切
ボトックス治療を受けた後は、日常生活での顎の使い方や睡眠中の食いしばりの有無、肩こりや頭痛の変化などをメモしておくと、次回の施術時に非常に参考になります。
治療の効果がどの程度現れているかを客観的に知る手段として、写真や日記のような記録を活用することもおすすめです。
まとめ
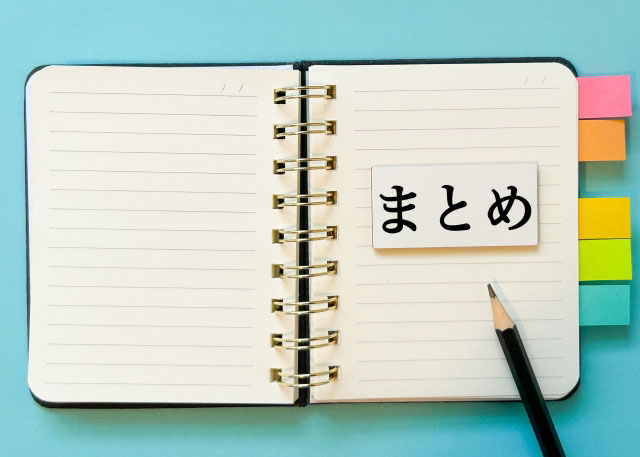
歯ぎしりや食いしばりは、放置すると顎・歯・筋肉・表情にまで影響を及ぼす深刻な問題です。
ボトックス注射は、噛む力を直接コントロールするという意味で非常に有効な治療法の一つですが、全ての人に万能というわけではありません。
正しい診断と目的に応じた治療方針を立てることで、負担軽減だけでなく、美容的な側面にもプラスの効果が期待できます。
まずは専門クリニックでカウンセリングを受け、無理のない範囲で症状に合った対策を始めてみましょう。
関連ページ
この記事の監修
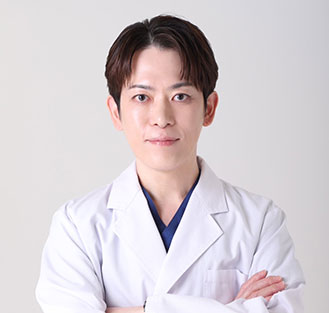
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463