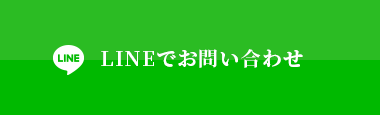防已黄耆湯で痩せた人の特徴とは?水太りやむくみに効く理由を解説

防已黄耆湯で痩せた人に共通する3つの特徴
防已黄耆湯を服用して「痩せた」と実感する人には、共通した体質の特徴が見られます。
この漢方薬は、誰にでも同じ効果を発揮するわけではなく、特定の体質の人に特に有効です。
これから紹介する3つの特徴は、防已黄耆湯が自分の体質に合っているかどうかを見極めるための重要な指標となります。
ご自身の体の状態と照らし合わせながら、確認してみてください。
もしこれらの特徴に多く当てはまるなら、防已黄耆湯がダイエットの有効な選択肢となる可能性があります。
特徴1:疲れやすく汗をかきやすい
疲れやすさと汗のかきやすさは、漢方でいう「気虚」の代表的なサインです。
「気」は生命活動のエネルギー源であり、これが不足すると少し動いただけでも疲れを感じやすくなります。
また、気には体表のバリア機能を担い、汗腺の開閉をコントロールする働きもあります。
そのため、気が不足すると汗の調節がうまくいかず、じっとりとした汗をかきやすくなるのです。
防已黄耆湯は、気を補う代表的な生薬である黄耆を含んでおり、エネルギー不足を改善し、汗の異常を整えます。
体力が回復することで活動的になり、結果として痩せたという状態につながりやすくなります。
特徴2:むくみやすく、特に下半身が太りやすい
むくみは、体内の水分代謝が滞っている「水滞」の状態を示します。
特に、夕方になると靴がきつくなる、足が重だるいなど、下半身にむくみが集中しやすいのは水太りの典型的な特徴です。
重力の影響で水分は体の低い位置に溜まりやすいため、下半身のむくみとして現れやすいのです。
これが慢性化すると、下半身太りの原因となります。
防已黄耆湯に含まれる防已や蒼朮には、体内の余分な水分を尿として排出させる「利水作用」があります。
この働きにより、むくみが解消されて体がすっきりし、体重が減少して痩せたという実感を得やすくなります。
特徴3:色白で筋肉がやわらかい体質
色白で肌がふっくらしており、筋肉にしまりがない、いわゆる「ぽっちゃり型」の体質も、防已黄耆湯が適している人の特徴です。
このような体質の人は、全体的に水分が多く、筋肉量が少ない傾向にあります。
触ると冷たく感じたり、脂肪がやわらかかったりするのも、余分な水分が体に溜まっているサインです。
筋肉は熱を生み出し、水分代謝を促すポンプの役割も担いますが、筋肉が少ないとこの働きが弱まり、水太りを招きやすくなります。
防已黄耆湯は、体内の水の巡りを改善することで、こうした水太り体質にアプローチし、体を内側から引き締めるのを助けます。
その結果、体重が落ちて痩せた状態へと導きます。
防已黄耆湯が水太りやむくみに効く仕組み

防已黄耆湯がなぜ水太りやむくみに悩む人のダイエットをサポートするのか、その効果は配合されている生薬の働きに基づいています。
この漢方薬は、単に体重を減らすだけでなく、体質そのものにアプローチするのが特徴です。
具体的には、体内の余分な水分を取り除く「利水作用」と、エネルギー不足を補い代謝を促す「補気作用」という、2つの主要な働きによって効果を発揮します。
ここでは、その2つの仕組みについて詳しく見ていきます。
6種類の生薬が体内の余分な水分を排出する
防已黄耆湯は、防已、黄耆、蒼朮または白朮、大棗、生姜、甘草という6種類の生薬で構成されています。
中心的な役割を果たすのが、防已と蒼朮です。
これらには強力な「利水作用」があり、体に溜まった余分な水分を尿として体外へ排出するのを促します。
黄耆は気を補い、体のバリア機能を高めて汗の量を調節します。
大棗、生姜、甘草は胃腸の働きを助け、全体の調和をとる役割を担います。
これらの生薬が相互に作用し合うことで、水分代謝が正常化し、むくみが改善されるため、水太りタイプのダイエットを効果的にサポートします。
「気」を補いエネルギー消費をサポートする
漢方における「気」は、人が活動するための根源的なエネルギーを指します。
気が不足した「気虚」の状態になると、疲れやすくなるだけでなく、基礎代謝も低下しやすくなります。
防已黄耆湯に含まれる黄耆には、この「気」を補う「補気(ほき)」という重要な働きがあります。
気を補うことで、胃腸の機能が高まり、食べ物から効率的にエネルギーを作り出せるようになります。
また、生命活動全体のエネルギー量が増加するため、基礎代謝の向上にもつながります。
疲れにくくなることで日中の活動量が増え、結果としてエネルギー消費量が増加することも、ダイエットを後押しする要因となります。
「脂肪太り」に効く防風通聖散との違いを解説
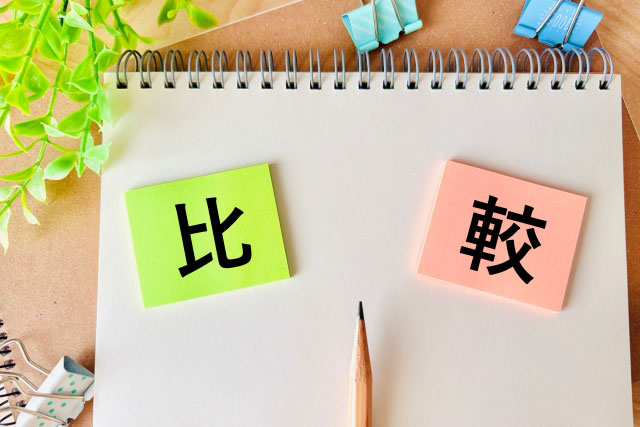
ダイエット目的で用いられる漢方薬として、防已黄耆湯のほかに「防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)」も有名です。
しかし、両者は適応する体質が全く異なります。
防已黄耆湯は、体力がなく疲れやすい、色白でむくみやすい「水太り」タイプの人向けです。
一方、防風通聖散は、体力が充実しており、お腹周りに皮下脂肪が多く、便秘がちな「脂肪太り」タイプの人に適しています。
防風通聖散は、体にこもった熱を冷まし、便通を促すことで不要なものを排出する作用が強いのが特徴です。
自分の太り方が水分によるものか、脂肪や便秘によるものかを見極め、体質に合った漢方薬を選ぶことが、ダイエット成功のための重要なポイントです。
防已黄耆湯の効果的な飲み方とタイミング

防已黄耆湯の効果を最大限に引き出すためには、正しい飲み方とタイミングを守ることが重要です。
漢方薬は、飲むタイミングによって吸収率や効果の現れ方が変わることがあります。
また、水で飲むのか、お湯で飲むのかといった点も、効果に影響を与える場合があります。
これから解説する基本的な服用方法を実践し、自分のダイエットに役立ててください。
もし飲み忘れてしまった場合の対処法なども知っておくと、継続しやすくなります。
食前または食間に水か白湯で服用する
漢方薬は、一般的に「食前」または「食間」に服用するのが基本です。
食前とは食事の約30分前、食間とは食事と食事の間のことで、食後2時間後が目安となります。
胃に食べ物が入っていない空腹時に服用することで、生薬の有効成分が効率良く吸収されやすくなります。
服用する際は、コップ1杯程度の水、または人肌程度の温度の白湯(さゆ)で飲むのがおすすめです。
白湯で飲むと胃腸への負担が少なく、体が温まることで生薬の吸収を助けるともいわれています。
お茶やジュースなどで飲むと、成分の吸収が妨げられる可能性があるので避けるようにしてください。
ダイエットを成功させるためにも、正しい服用方法を心がけましょう。
服用前に知っておきたい副作用と注意点

防已黄耆湯は自然由来の生薬から作られていますが、医薬品であるため副作用のリスクが全くないわけではありません。
安全に服用を続けるためには、どのような副作用が起こりうるのか、またどのような点に注意すべきかを事前に理解しておくことが不可欠です。
特に、他の薬を服用している方や、持病のある方は注意が必要です。
これから説明する内容をよく確認し、自分の体調に異変を感じた際には適切に対応できるようにしましょう。
注意すべき初期症状と副作用
防已黄耆湯の副作用として報告されているものには、皮膚症状として発疹やかゆみ、消化器症状として食欲不振や胃の不快感、吐き気などがあります。
これらは比較的軽度なものですが、症状が現れた場合は服用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
また、頻度は稀ですが、重篤な副作用として「偽アルドステロン症」「間質性肺炎」「肝機能障害」が知られています。
偽アルドステロン症の初期症状は、手足のだるさ、しびれ、むくみ、血圧の上昇などです。
間質性肺炎では、空咳、息切れ、呼吸困難、発熱が見られます。
肝機能障害では、倦怠感、食欲不振、黄疸などが起こります。
これらの症状に気づいた場合は、直ちに服用をやめて医療機関を受診する必要があります。
他の漢方薬や利尿薬との併用は医師に相談を
防已黄耆湯を服用する際は、他の薬との飲み合わせに注意が必要です。
特に、甘草を含む他の漢方薬と一緒に服用すると、甘草の摂取量が過剰になり、偽アルドステロン症のリスクが高まる可能性があります。
複数の漢方薬を自己判断で併用することは避けてください。
また、防已黄耆湯には利尿作用があるため、病院で処方される利尿薬など、同じような作用を持つ薬と併用すると、作用が強く出すぎて脱水や電解質異常を引き起こす危険性があります。
現在、何らかの治療を受けている方や、他のサプリメントを含め薬を服用している場合は、防已黄耆湯を始める前に必ず医師や薬剤師に相談し、安全性を確認した上でダイエットに取り入れましょう。
防已黄耆湯を飲んでも痩せない時に考えられる理由

防已黄耆湯を服用しているにもかかわらず、なかなか痩せないと感じる場合、いくつかの理由が考えられます。
最も多いのが、そもそも体質が防已黄耆湯に合っていないケースです。
例えば、むくみではなく固太りや脂肪太りが原因の場合、この漢方薬では効果は期待しにくいでしょう。
また、効果を実感するにはある程度の期間が必要なため、服用期間が短すぎる可能性もあります。
さらに重要なのは、漢方薬はあくまで体質改善をサポートするものであり、それだけで痩せるわけではないという点です。
暴飲暴食をしていたり、全く運動をしていなかったりするなど、生活習慣が乱れていては効果は現れません。
思うように結果が出ない時は、体質との相性や生活習慣を見直すことが必要です。
防已黄耆湯に関するよくある質問

防已黄耆湯を使ったダイエットを検討している方から、多くの質問が寄せられます。
効果を実感できるまでの期間や、市販薬と処方薬の違いなど、実際に服用を始める前に知っておきたい点は多いでしょう。
ここでは、そうした疑問の中でも特に代表的なものをQ&A形式で解説します。
これから防已黄耆湯を試してみたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
正しい知識を持つことで、より安心してダイエットに取り組むことができます。
Q1. 効果を実感できるまでの期間はどのくらい?
防已黄耆湯の効果が現れるまでの期間には個人差があります。
体質や症状の程度によって異なるため、一概には言えません。
一般的に、むくみの軽減といった水分の排出に関する効果は、早ければ1〜2週間程度で実感できることがあります。
しかし、体重減少や体質改善といったダイエット効果を期待する場合は、最低でも1ヶ月以上の継続的な服用が一つの目安とされています。
漢方薬は、体質を根本からゆっくりと変えていくことで効果を発揮するため、焦らずに続けることが大切です。
もし1ヶ月以上服用しても全く変化が見られない場合は、薬が体質に合っていない可能性も考えられるため、医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
Q2. ドラッグストアの市販薬でも効果はある?
ドラッグストアなどで販売されている市販の防已黄耆湯でも、効果を期待することは可能です。
医師の処方箋がなくても手軽に購入できるため、漢方ダイエットを試してみたい方にとっては便利な選択肢となります。
市販薬は、定められた用法・用量を守って正しく使用すれば、むくみの改善や水太りへのアプローチができます。
ただし、市販薬を選ぶ際は、自分の体質に本当に合っているかを自己判断する必要があります。
購入する際には、常駐している薬剤師や登録販売者に相談し、自分の症状や体質を伝えた上でアドバイスをもらうと良いでしょう。
これにより、ミスマッチを防ぎ、より安全にダイエットに取り組むことができます。
Q3. 処方薬と市販薬では何が違うの?
医療機関で処方される防已黄耆湯とドラッグストアなどで購入できる市販薬の主な違いは、有効成分の含有量と健康保険の適用の有無です。
一般的に、医療用の方が市販薬に比べて生薬の配合量が多く設定されている傾向があります。
そのため、よりしっかりとした効果を期待する場合は、医師の診断のもとで処方される医療用が選択肢となります。
また、医療機関で処方された場合は健康保険が適用されるため、自己負担額を抑えられることが多いです。
一方、市販薬は全額自己負担ですが、診察なしで手軽に購入できるメリットがあります。
どちらを選ぶかは、自分の症状の程度や利便性などを考慮して判断するとよいでしょう。
まとめ

防已黄耆湯は、疲れやすく、むくみがちで筋肉がやわらかい「水太り」タイプの体質を持つ人のダイエットに適した漢方薬です。
この漢方薬で痩せた人は、自身の体質と薬の効能が合致していたケースが多いと考えられます。
6種類の生薬が体内の余分な水分を排出し、不足した「気」を補うことで、水分代謝とエネルギー代謝の両面から体質改善をサポートします。
しかし、脂肪太りの人が飲んでも痩せない可能性が高く、効果を実感するには生活習慣の見直しも不可欠です。
副作用のリスクもあるため、服用前には必ず専門家に相談し、自分の体質を正しく理解した上で、安全にダイエットに取り入れることが求められます。
関連ページ
提携クリニック
この記事の監修
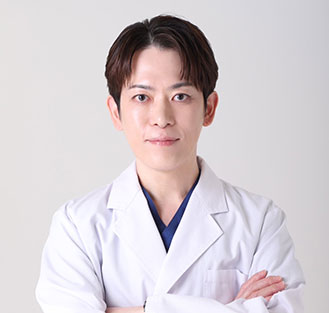
小西 恒
2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。
【資格・所属学会】
ボトックスビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® 認定医、
ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、
日本美容外科学会(JSAS) 正会員、
日本産科婦人科学会 会員、
日本産科婦人科学会 専門医、
日本医師会認定産業医、
母体保護法指定医


 カウンセリング
カウンセリング LINEで
LINEで
 050-1724-3463
050-1724-3463